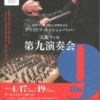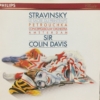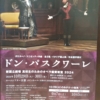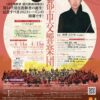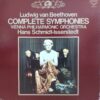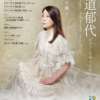アクセルロッド&京都市交響楽団による演奏会(チャイコフスキーの≪悲愴≫ 他)を聴いて

今日は、アクセルロッド&京都市交響楽団による演奏会を聴いてきました。演目は、下記の3曲。
●チャイコフスキー ≪ハムレット≫
●R・シュトラウス ≪四つの最後の歌≫(独唱:森麻季さん)
●チャイコフスキー ≪悲愴≫
R・シュトラウスの歌曲を、チャイコフスキーの2曲で挟むという、ちょっと変わった構成となっていますが、アクセルロッドによるプレトークを聞くと、「生と死」をテーマにしたプログラムだとのこと。
アクセルロッドは、2020年から2023年3月まで京響の首席客演指揮者を務めていましたが、退任後に京響の指揮台に登るのは今回が初めて。およそ2年ぶりに戻ってきたことになります。
2010年1月のN響定期で初めてアクセルロッドを聴いて以来、私は篤い信頼を寄せています。そのN響の定演での前プロの≪スラヴ行進曲≫があまりに見事で、度肝を抜かれたものでした。
京響では、2021年11月の≪英雄の生涯≫をメインに据えた演奏会、2022年9月のマーラーの≪復活≫を採り上げた演奏会、2023年3月の≪春の祭典≫をメインに据えた演奏会と、3つの実演に触れてきましたが、いずれも大きな感銘を与えてくれる演奏を繰り広げてくれています。とりわけ≪英雄の生涯≫では、こんなにも素晴らしい≪英雄の生涯≫の実演には滅多に巡り会えるものではないだろう、と思えるほどの見事な演奏を聞かせてくれた。
アクセルロッドによる演奏の美質は、折り目正しくて、どこにもハッタリのない音楽づくりを基調としながら、力強さや生命力の豊かさを備えている演奏を聞かせてくれるところにあるように思えます。逞しくて感興の豊かな音楽が響き渡ってゆく。そのうえで、表情が毅然としている。音楽づくりが克明で、音楽がキリっとした佇まいを示すこととなる。その結果として、作品の素晴らしさや偉大さが、ありのままの姿で現れ出てくる。
今回のチャイコフスキー2曲と、R・シュトラウスの白鳥の歌となった≪四つの最後の歌≫では、どのような演奏を繰り広げてくれることだろうか。≪ハムレット≫を実演で聴くことができるというのも、貴重な機会であります。そんなこんなを含めて、なんとも楽しみな演奏会でありました。
また、森麻季さんの独唱にも注目。
森さんの歌の特徴は、清澄にして、可憐なところにあるように思えます。そして、高音域の響きが透き通るようで、伸びやか。そんなこんなによって、とてもチャーミングな歌が繰り広げられることとなる。そのような特徴からすると、哀惜にして寂寥感が漂い、甘美でありつつも玄妙な音楽世界の広がる≪四つの最後の歌≫は、森さんにはちょっと相性が良くないようにも思われるのですが、実際にはどのような歌になるのだろうかと、こちらも楽しみでありました。
それでは、本日の演奏会をどのように聴いたのかについて書いてゆくことに致します。

まずは前半の2曲から。
≪ハムレット≫、期待通りの素晴らしい演奏でした。頗る雄渾な演奏となっていた。
生命力に溢れていた。そして、音楽の歩みが克明であり、なおかつ、力強くもありました。音楽がキビキビとしていて、推進力に満ちていた。そのうえで、音楽が有機的に絡み合っていた。音楽のフォルムがキリッと引き締まっているのに、豊かな響きがしていた。そう、凝縮度の高い演奏が繰り広げられていながら、十分に豊麗でもあったのです。
しかも、ドラマティックでいて、ロマンティックな感興にも不足はなかった。そのような性格が、チャイコフスキーの音楽には誠に相応しいと言えましょう。チャイコフスキーならではの旋律美を存分に味わいつつも、過度に耽美的になるということもなかった。
総じて、バランス感覚に秀でていた演奏だったと言いたい。そして、アクセルロッドの類稀な音楽性の豊かさがクッキリと刻まれていた演奏だったとも言えましょう。
一方の≪四つの最後の歌≫は、森さんによる独唱が非力なものとなっていて、もどかしい思いを募らせました。
オケに声が掻き消されることがしばしば。なるほど、清澄な歌声で、歌いぶりがしなやかではあったものの、歌に貫禄がない。この歌曲では、哀惜感も必要ですが、恰幅の良さや貫禄といったところも欲しいところ。その辺りが、かなり不足していた歌となっていたのでした。
概して、作品の実像が聴き手に届いてこない歌唱だった。そんなふうにも言いたい。
なお、本日のコンマスは豊嶋泰嗣さんが務めておられたのですが、第3曲目でのコンマスソロ、素晴らしかった。艷やかにして清らかで、なおかつ、キリッとした音楽が奏で上げられていました。森さんの歌からはなかなか見えてこなかった「音楽の実像」といったものが、ハッキリと伝わってくるソロになっていました。
≪四つの最後の歌≫でのアクセルロッドの音楽づくりは、森さんの歌を慈しむようなものだった(或いは、極力声を掻き消さないように配慮していた、とも言えそう)。そのため、頗る繊細な演奏ぶりとなっていた。とは言え、アクセルロッドならではの逞しい息吹、といったものは随分と減退していたように思えた。聴いていて、じれったさを感じたものでした。
ここからはメインの≪悲愴≫について、となります。
素晴らしい演奏でありました。しかしながら、これまでに聴いてきたアクセルロッドによる演奏ほどには強い感銘を受けるには至りませんでした。それと言いますのも、本日の≪悲愴≫は、これまでの演奏と比べると、毅然とした態度に徹していたとは言い切れなかったように感じられたからであります。耽美的な色合いを見せる箇所が散見されもした。
例えば、第1楽章の展開部では、周囲に目もくれずに疾走してゆく様を見せてくれ、これまでのアクセルロッドの演奏スタイルそのものが示されていました。主情を挟むようなことなく、音楽を思いっ切り掻き鳴らしていた。また、最終楽章では、ドライな音楽にならない範囲で、毅然とした演奏を繰り広げてくれていました。アゴーギクの変化も、音楽の歩みに即したもので、そこからは決然としたロマンティシズムが滲み出していた。プレトークで、ホルンのゲシュトップ奏法に触れることが多かったのですが、最終楽章終盤でのゲシュトップ(126小節目以降)は、断末魔の呻き、といった様相を呈していた。
かように、アクセルロッドならではの音楽づくりが随所に見られました。音楽をシッカリと抉っていきながらの演奏だった。そんなふうにも言いたい。
しかも、総じて逞しい生命力を宿していた演奏となっていた。息遣いが豊かであった。また、響きがダブつくようなことがなく、キリッとした佇まいを見せながらも、豊かな響きがしていた。
そんなこんなのうえで、熱狂的でありつつも、過度にならない範囲で暗鬱な音楽が響き渡っていた。そのような音楽づくりが、≪悲愴≫には誠に相応しかった。
最初に「素晴らしい演奏だった」と書きましたのも、この辺りの演奏ぶりに対してであります。
その一方で、アクセルロッドにしては珍しくと言いましょうか、恣意的な表現も散見されたのであります。例えば、第1楽章の展開部が終わろうとしている箇所で、小節をまたぐことをためらうかのように、凄まじいまでのラレンタンドを掛けたりしていた。また、第3楽章では、足踏みをするかのように急激にテンポを落として(実際に、アクセルロッドは指揮台の上で足踏みをしていました)、音楽に句読点を打つような意図が示されたりしていた。
これらの表現は、感極まっての上での、やむにやまれぬ心境から湧き出てきたものだったのでしょう。その思いを、理解できない訳ではありません。なおかつ、そのような措置が、次から次と頻発した訳ではありませんでしたので、煩わしさを覚えるほどではありませんでした。とは言うものの、私には、「ちょっとやり過ぎなのでは」と思われたものでした。音楽のフォルムが崩れてしまっていた、とも感じられたのでありました。なおかつ、悪い意味で異彩を放つこととなっていた。そこのところが残念でありました。
そのような、些事においての不満はありました。とは言うものの、総体的に見れば素晴らしい演奏だったと言いたい。アクセルロッドの美質を、随所に見出すことのできた演奏だったとも思います。
なお、本日の聴衆は、最終楽章の最後の音が鳴り止んだ後も、演奏者たちが緊張の糸を解くまで、フライングで喝采を送ることなく静寂を保持してくれていました。更には、第3楽章から最終楽章に入る際、演奏者たちは緊張を解かずにそのまま最終楽章に突入した(とは言うものの、アタッカで入ったというほどに間隙が短かった訳ではありませんでした)のですが、その間、物音を立てるようなことはありませんでした。素晴らしい聴衆だったと思います。