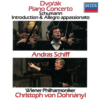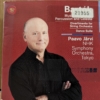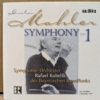ホロヴィッツによるシューマンの≪幻想曲≫を聴いて

ホロヴィッツによるシューマンの≪幻想曲≫(1965/5/9 カーネギーホールライヴ)を聴いてみました。
シューマンの作品の大半は、良い意味でカオスな音楽と呼べそうな様相を呈しているのではないだろうか。そんなふうに思っています。情熱や焦燥や憂鬱や、といったものが、ないまぜになった音楽が多い。その先には、得体のしれない「熱狂」(狂気と言っても良いかもしれません)のが潜んでいる。そして、豊麗さを示すようなことも多い。
そこへゆきますと、ここでのホロヴィッツによる≪幻想曲≫は、一つ一つの音や曲想などが、秩序だったものとして提示されている。理性的でもある。ある種、明確に分離され過ぎているようにも思えます。キリっと引き締まっている。であるが故に、シューマンならではのカオスが、今一つ薄い。熱狂的な演奏であるとも言い切れそうにない。
その一方で、整然としていつつも、勇壮で壮大な音楽世界が広がっている。更に言えば、荘厳な音楽が鳴り響いている。そのうえで、音の粒が鮮やかで、かつ、響きは美しい。
幻想的(ファンタスティック)というよりも、かなり現実的な音楽になっているようにも思えるのですが、誠にワンダフルであり、ロマンティックでもあると言いたい。
そんなこんなは、いかにもホロヴィッツらしいところだとも言えましょう。
甘さ控えめの、辛口なシューマン。しかも、頗る充実感の高い演奏。
なんとも立派な、そして、ホロヴィッツならではの魅力を備えている、素敵な素敵なシューマン演奏であります。