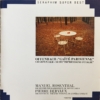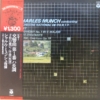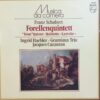内田光子さんによるピアノリサイタル(ベートーヴェンのピアノソナタ第30,31,32番)の京都公演を聴いて
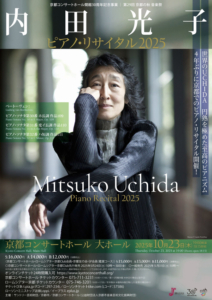
今日は、内田光子さんのピアノリサイタルの京都公演を聴いてきました。演目は、ベートーヴェンのピアノソナタ第30,31,32番。
個人的には、現役のピアニストの中では、ツィマーマンとともに最も敬愛している内田光子さんによる実演。しかも、ピアノ音楽の最高峰だと考えておりますベートーヴェンの最後の3つのピアノソナタを弾いてくれる演奏会。
これはもう、究極の演奏会だと言えましょう。そのような演奏会に立ち会えることに、心が震える思いがしたものです。
なお、今年の来日公演は、京都と水戸、あとは東京で2公演と、4回が組まれています。今晩は、その初日。
内田光子さんのソロリサイタルを聴くのは、2017年のザルツブルク音楽祭以来で、これが2回目。
あの時は、モーツァルトのハ長調のソナタK.545の第2楽章が終わろうとしている箇所で、急におかしくなった内田さん。とは言うものの、それ以外は、内田さんならではの精妙にしてニュアンス豊かな演奏に、深い感銘を受けたものでした。
本日もまた、きっと、あの時の音楽づくりと同じ地平に立ったものとなることだろう。そのような音楽づくりが施されるであろうベートーヴェンの最後の3つのソナタに触れることができる。いったい、どれだけの感銘を受けることになるのか、想像がつかないといった状況で、会場に向かったのでした。
それでは、本日の演奏会をどのように聴いたのかについて書いてゆくことに致します。

前半の2曲を聴いての印象は、あまり芳しいものではありませんでした。と言いましょうか、今日はかなり調子が悪いのでは、と思えてならなかった。
まずもって、ミスタッチがとても多かった。しかも、どうといったことのなさそうな箇所でもミスタッチを犯していた。とりわけ、第31番の終わり間近の辺りでのミスタッチの連続には、驚かされたものでした。2017年のザルツブルクで聴いたウィドマンの作品では、ヴィルトゥオジティの高さが痛感することができました。そんな内田さんが、こんなにも多くのミスタッチを犯すとは。いったいどうしたことなのだろうという思いを強くしたものでした。集中力が低いようにも思えた。そして、心なしか、疑心暗鬼な音楽になっているようにも感じられた。
更には、流麗さに乏しかったようにも思えたものでした。
内田さんによる演奏は、没入感が強く、聴衆のためにピアノを弾いているというよりも、自分のために弾いている、といった傾向にあると思えます。とてもストイックでもある。そして、凝縮度や結晶度が頗る高い。とは言え、感受性が途轍もないほどに強いこともあって、音楽が豊かに息づいていて、瑞々しさを備えたものとなっている。そのために、音楽が淀みなく流れてゆく。従来の内田さんの演奏は、そのような性格の強いものだと看做しているのですが、前半の2曲では、そのようになっているとは言い切れなかった。そこのところにも、もどかしさを覚えたものでした。
そのような演奏ぶりから聞き取れた内田さんによるベートーヴェンは、決して強靭であったり、豪壮であったり、といったものではありませんでした。それよりももっと、内省的なベートーヴェンになっていた。第30番の出だしなどは、ためらいがちに開始されていた。
また、概してテンポが遅い。それは第31番において顕著でした。第1楽章の展開部などは、一音一音を踏みしめながら進んで行っていた。
そのような中でも、内田さんならではのデリケートな音楽づくりは、随所で見られました。特に、31番の第3楽章の序奏部、「嘆きの歌」が始まるまでの箇所は、音楽に吸い込まれてしまいそうなほどの精妙さがありました。また、最初にフーガが提示される箇所などは、極度なまでの弱音で、しかも、頗るゆっくりとしたテンポが採られていて、珠のような美しさに息をのんだものでした。
更には、30番の最初の2つの楽章は前奏曲のようなものであり、変奏曲の第3楽章からが本編だと看做せそうですが、その第3楽章では、慈しみ深くて、深遠な音楽が鳴り響いていました。この辺りは、内田さんの真骨頂だと言えましょう。
そのように、グッと惹き込まれる場面も多い演奏ではありましたが、期待があまりに大きかったこともあって、やや調子の狂ってしまった前半でありました。
そのような前半に対して、後半の第32番では、心を鷲摑みにされました。
音楽が鳴り止んでからというもの、しばらくは放心状態でありました。言葉も失った。Bravaの声を掛けることなんて、とてもできなかった。拍手を力強く叩くこともできない。場内には立ち上がって拍手を送る聴衆も多くいましたが、立ち上がることもできない。そう、身体から力が抜けてしまい、呆然としていたのでした。そして、ただただ、今まで鳴り響いていた音楽を噛み締めるだけでした。
第32番でも、ミスタッチはありました。しかしながら、そのようなことはもう、関係ありません。と言いつつも、全体的に、前半の2曲に比べると、集中力の高い演奏になっていたように思えたものでした。そして、作品の性格もあって、前半の2曲よりも豪壮な演奏になっていた。そして、流麗なものになっていたようにも思えた。
第1楽章は、主題提示部をリピートしてくれていました。そのこともあって、巨大な建造物が聳え立ってゆくような趣きを湛えてもいた。
とは言うものの、至る所で内田さんならではのデリケートな音楽が示されていった。テンポは相変わらずに遅めで、一歩一歩踏みしめてゆくような音楽になることもしばしば。
第2楽章の冒頭は、繊細な音で、ジックリと紡ぎ上げてゆく。それがまた、心に染みるものになっていた。次第に音楽は高調していくのですが、その様がまた、堅固な建造物が建ってゆくような趣きを湛えることとなっていた。その先に訪れる第3変奏、あの個性的にリズミカルに躍動する変奏部分では、十分に力強かったのですが、決して過度に賑々しくなったり、浮足立ったり、といったようなことはなく、しっとりとした情感が込められていたのには、驚かされたものでした。
そして、長い長い終結部を迎えるですが、ここからはもう、別世界に誘われたような音楽になっていった。儚いとか、繊細だとか、そういった表現を超越した音楽でありました。聴いていて、魂が抜かれていくような思いを抱いたものでした。そして、静寂の内に音楽は終わり、魂が昇華していった。
アンコールはありませんでした。このような音楽を聴いた後にはもう、何も聴きたくありません。ピアニストもまた、何も演奏したくないことでありましょう。アンコール無しというのは、至極真っ当なことだと思えてなりませんでした。
演奏会場を後にする時は、足早に歩けませんでした。私は、普段は歩くのが速い方で、周囲の人を追い抜きながら歩くのですが、今日は、周りから追い抜かれながらしか歩くことができなかった。やはり、魂が抜かれたままだったのでした。