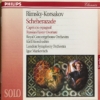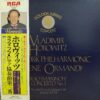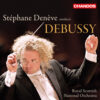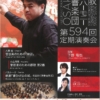藤岡幸夫さん&関西フィルによる演奏会(ヴェルディの≪レクイエム≫)を聴いて

今日は、藤岡幸夫さん&関西フィルによる演奏会を聴いてきました。演目は、ヴェルディの≪レクイエム≫。
独唱陣は、並河寿美さん(ソプラノ)、福原寿美枝さん(メゾ・ソプラノ)、福井敬さん(テノール)、大西宇宙さん(バリトン)という、充実した陣容です。
先週末の山下一史さん&大阪交響楽団によるヴェルディの≪レクイエム≫に続いて、2週連続で同曲聴いたことになります。その、山下さんによる演奏が、なんともケレン味のないもので、かつ、充実度の高い演奏が繰り広げられていて、大いに感心させられたたけに、本日の藤岡さんが全体を統率する演奏が、どのようになるのか、その比較も含めて興味深いところでありました。
また、独唱陣の顔ぶれが頗る豪華なものになっているのが、なんとも嬉しいところ。とても楽しみでありました。とりわけ、並河さん、福井さん、大西さんに大きな期待を寄せていたものでした。
なお、この曲では非常に珍しいことになりますが、休憩を挟んでの上演とのこと。この曲での休憩を入れての公演は、私は初めてであります。
途中で雰囲気が分断されないか、その点が心配でありました。
ちなみに、プレトークで藤岡さんが紹介された話によりますと、ヴェルディが自ら≪レクイエム≫を演奏する際には、必ず休憩を挟んでいたようです。そのこともあって、藤岡さんがこの曲を採り上げる際には、必ず休憩を挟むことにしているとのこと。また、「ラクリモーサ」の重たい気分(と、藤岡さんは仰っていましたが、あのナンバーは重たいと表現するには、少し違うように思えたものでした。それよりも、清澄な音楽世界が広がるナンバーなのではないでしょうか)を引きづって、そのままその後に進むことができないから、とも仰っておられました。
更には、プレトークで藤岡さんは、前半が終わったら拍手をしてくださいと要望されていましたが、私は拍手をすることは控えました。それは、演奏の出来栄え云々に依るのではなく、作品を鑑賞する気分を途切らせたくないから。ちなみに、2001年1月27日、ミラノのサンマルコ教会(ヴェルディは、没後、この教会に眠っています)で聴いてきた、ヴェルディの没後100年を記念してのムーティ&ミラノ・スカラ座による≪レクイエム≫では、全曲が終わっても、聴衆は拍手をしませんでした。その雰囲気は、なんとも異様なものでした。そして、とても厳かなものでありました。その体験から、この曲では極力拍手は控えたい、という思いを抱くようになったものです。
(そうは言いながらも、先週の山下さんによる演奏会では、盛大な拍手を送ったのですが。)
と、前置きはここまでに致しまして、本日の演奏会をどのように聴いたのかについて、書いてゆくことにしましょう。

まずは、休憩を挟んだことについて。私が開演前に抱いていた心配は、杞憂に終わりました。
演奏者たちにとって、それまでに築き上げたものが一旦ご破算になり、また一から作り直さなければならなくなるだろう、といったことも懸念されたのですが、すんなりと作品の音楽世界に溶け込んでいけていたようです。それはまた、私も然りでありました。
さて、演奏ぶりはと言いますと、頗るドラマティックなものでありました。プレトークで、ドラマティックという言葉を5回以上は使っていたと思われる藤岡さん。そのような藤岡さんの作品観がよく現れていたのではないでしょうか。しかも、それが空回りしていなかった。とても輝かしくもあった。そこには、関西フィルの艶のある、明るい響きが大きく貢献していたとも思われます。
とりわけ、「ディエス・イレ」でのバスドラの強調は凄まじいものがあり、かつ、効果的でありました。この点も、プレトークで触れておられたものでした。藤岡さんは、このバスドラに、ヴェルディが表現したかった「怒り」が込められているのだ、と見做しておられるとのことでもありました。
但し、「ディエス・イレ」の53小節目から61小節目にかけて、再三にわたって現れる木管楽器による上昇音型を、藤岡さんはあまり重視されていなかったようで、周囲の音の中に埋没してしまってハッキリと聞こえてこなかったのには、疑問を抱いてしまいました。63小節目以降にも同様の動きがありますが、この辺りまでくると、周りの音は静かになっていますので、ハッキリと聞き取れた。これは一例で、似たような、「あれっ?」と思わせる箇所が幾つか見受けられたものでした。
とは言うものの、演奏は、全体的に見事なものだったと言いたい。プレトークで藤岡さんは、この作品への思い入れの強さをアピールされていましたが、そのことの良く理解できる演奏ぶりだったとも思えました。
先週の山下さんによる演奏は、ケレン味のない実直な音楽づくりを土台としながら、劇的な要素も過不足なく加味されたものになっていました。それに比べると、本日の藤岡さんによる演奏は、かなり劇性の強い演奏でありました。ストイックな要素は殆ど見受けられず、総じて開放的な音楽づくりが為されていた。とは言いつつも、プレトークでも触れておられていましたが、弱音を大事にしながら、丁寧な表情付けが為されてもいた。ただそれが、果てしないまでの静謐を生むというよりは、劇性との対比を描き上げるために為されていた、といった印象を受けたものでした。そう、音楽づくりの上での技術的な手段として、そのような音楽表現が施されていたのだ、といった感じを受けたのであります。この作品への共感が薄く思えたと言えば言い過ぎでありましょうが、ちょっと予定調和だったとも思えた。本日の藤岡さんの演奏に対する不満の一つが、そこの部分でありました。
とは言いながらも、ドラマティックでダイナミックで、この作品のツボをシッカリと押さえた演奏だったのではないでしょうか。この作品に相応しい壮麗な音楽世界が築かれてもいました。
ちなみに、弦楽器のプルトの数は6-5-4-3.5-3と、山下さん&大阪交響楽団による演奏よりも更に規模が小さかった。それでも、十分に逞しくて、輝かしくて、充実度の高い演奏が繰り広げられていたのには、感心させられました。思えば、ピットに入ってヴェルディのオペラを演奏するとなれば、そのスペースの関係上、このくらいの編成か、或いはもっと切り詰めなくてはなりません。それを考えると、十分な規模の編成だったのでありましょう。
なお、「リベラ・メ」の382小節目、Tutta forza(全力を込めて)と書かれた箇所で、藤岡さんは思いっ切りテンポを落として、ルバートを掛けながら音楽をタップリと響かせたのでした。この手法は、他の多くの演奏でも見受けられますが、大概は、その2小節目辺りからテンポを上げていって、早めに元のテンポに戻します。しかしながら、藤岡さんは、遅いテンポをかなり長く維持されていた。そのことによって、重々しくて、かつ、頗る彫りが深い音楽が鳴り響くことになったのであります。その様は、誠に印象的であり、効果的でもあった。それは、計算によって生み出された表現ではなく、この部分への深い共感に依るものだったと思えてなりませんでした。
さて、ここからは独唱陣について。音域の低いほうから書いてゆくことに致しましょう。
大西さんはバリトンと表記されていますが、なるほど、明るい色調をした声音によって、朗々と歌い上げてくれていました。決して深々としていなかった訳ではありませんが、その点では、先日の山下さんによる公演での伊藤貴之さんのほうが優っていたと言いたい。威厳も、伊藤さんのほうが強かった。その一方で、大西さんによる歌は、暖かみを帯びていて、歌い口が滑らかだった。歌に艶やかさがあった。
この辺りは、バスとバリトンによる違いが主たる要因でありましょう。この作品にとって、どちらのほうが好ましいかと言えば、個人的にはバスのほうに軍配を上げたいところですが、大西さんによる歌唱も、頗る魅力的だったことに違いはありません。必要十分にドッシリと構えた歌になってもいました。
テノールの福井さんは、ドラマティックにして、リリカルなものでした。福井さんの歌に接すると、しばしば思ってしまうことなのですが、その歌い口は、ヴィンチェンツォ・ラ・スコーラを彷彿とさせる。
そのうえで、とても凛としていた。輝かしさと、柔らかさが何の矛盾もなく同居していた歌だったとも言いたい。そこに、福井さんならではの魅力が詰まっていたのであります。
なお、時折、マルッカートな歌いぶりを見せてくれていたのが、実に個性的であり、かつ、印象的でありました。この作品では、あまり例を見ない歌い方だっただけに、驚かされもしたものでした。
メゾ・ソプラノの福原さんは、個人的には、4人の独唱者の中で最も心打たれる歌を披露してくれていたと思えたものでした。
とてもドスの効いた歌いぶりでありました。それ故に、≪仮面舞踏会≫のウルリカが似合うのでは、と思えたものでした。しかも、とても深々としていた。情感豊かでもあった。激情的な色合いから、慰めに満ちた表情まで、実に多彩でもあった。
メゾ・ソプラノならではの魅力が詰まっていた、頗る魅力的な歌でありました。先日も書きましたが、この曲では、メゾ・ソプラノによって音楽上の新たな局面が展開されてゆくことが多いだけに、このように充実度の高いメゾ・ソプラノを配役できたことは、とても意義深いことだと言いたい。
ソプラノの並河さんは、基本的にはドラマティックでありつつも、繊細さや柔らかさも兼ね添えている歌いぶりでありました。しかも、十分に清澄でもあった。そういったコントラストのクッキリとした歌を披露してくれていて、なんとも魅力的でありました。
ただ惜しむらくは、先日の森谷さんと同様に、「リベラ・メ」の170小節目でのppppがビタっと決まらなかった。弱音でオクターヴ上に昇っていったものの、声がふらついてしまって、安定感を欠いていた。ここ、大変難しいのでしょうが、それでもやはり、ピタッと決めて欲しいものです。
と、独唱陣について色々と書いてきましたが、本日の演奏が充実したものになったのも、4人のソリスト達の貢献度は頗る高いと言えましょう。大いに喝采したいところであります。
合唱団もまた、見事でありました。人数は、先週の山下さん&大阪交響楽団による演奏会の1.5倍くらいはいたでしょうか。そのこともあって、響きに分厚さがあって、ヴェルディの音楽に不可欠な輝かしさも十分でした。しかも、藤岡さんのこだわりも反映されていたようで、シラブルを明瞭に発することが多く、そのことによってニュアンス豊かで、かつ、意義深さを備えた合唱になっていたと思えたものでした。
多少は疑問に思えた点もありましたが、総じて、聴き応え十分な演奏でありました。
十分な満足感を抱きながら、会場を後にしたものでした。