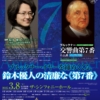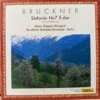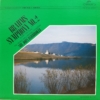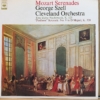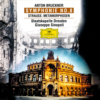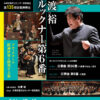ムローヴァ&プレヴィン&ロイヤル・フィルによるショスタコーヴィチのヴァイオリン協奏曲第1番を聴いて

ムローヴァ&プレヴィン&ロイヤル・フィルによるショスタコーヴィチのヴァイオリン協奏曲第1番(1988年録音)を聴いてみました。
NML(ナクソス・ミュージック・ライブラリー)に収蔵されている音盤での鑑賞になります。
ムローヴァによるこの曲は、2013年の4月に、N響の定期演奏会で実演に接しています。指揮者は、初代の東京クァルテットの第1ヴァイオリン奏者だったウンジャン。
そのときの演奏はと言いますと、緊張の糸の張り詰めた演奏ぶりで、頗る集中度の高いものとなっていました。この作品ならではの峻厳にしてシリアスな雰囲気も、演奏の端々から滲み出ていた。そのうえで、ピュアな美しさを湛えたものとなっていた。
それはそれは、聴いていて圧倒される演奏でありました。感銘度が頗る高くもあった。
さて、この音盤に刻まれている演奏も、N響との実演を彷彿とさせるものとなっています。ムローヴァならではの、集中力の高くて、冴え冴えとした演奏が繰り広げられている。全編を通じて、研ぎ澄まされた感性に裏打ちされた音楽が鳴り響いているとも言えましょう。玲瓏な演奏だとも言いたい。
この作品に相応しい、シリアスでシニカルな雰囲気も十全に表されています。そして、ピンと張りつめた緊張感が作品全体を貫いている。
冒頭部分などは、寒々とした音楽が鳴り響いています。寂寥たる音楽だとも言えそう。しかも、弱音主体の演奏ぶりであっても、音楽が痩せるようなことは全くない。
更には、この作品のキモとも言えそうな第3楽章から第4楽章へと繋がってゆく長大なカデンツァ(と言いますか、モノローグのような箇所)での緊張感は、背筋の凍るような凄みすら感じさせられます。その後に続く第4楽章では、ホットにして、躍動感に溢れた音楽が奏で上げられている。それはもう、切れば血の出るような音楽となっている。
そんなこんなのうえで、テクニックの切れが抜群。それも、作品の内奥に鋭く切り込んでいくためのみに鮮やかなテクニックが駆使されている、といった演奏ぶりとなっている。そして、音の粒が鮮やかで、かつ、音色は艶やか。
そのようなこともありまして、凛とした美しさを湛えた音楽が鳴り響くこととなっています。このことは、感覚的な面のみならず、内面的な面においても、更には、ここでの演奏が示している佇まいにおいても、当てはまりましょう。
そんなムローヴァをサポートするプレヴィンもまた、鮮烈かつ丁寧な演奏を繰り広げてくれています。演奏全体が、生彩感に富んだものとなっている。そして、作品が持つ生命力を的確に放出させながら、ピュアな美しさを湛えた音楽を奏で上げてくれている。
これはもう、畏敬の念を抱かせるほどの、なんとも素晴らしい演奏であります。