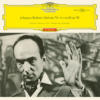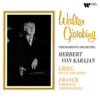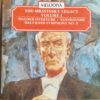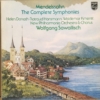デスピノーサ&京都市交響楽団による第九演奏会の初日を聴いて

今日は、デスピノーサ&京響による第九の初日を聴いてきました。
独唱陣は、下記の通りになります。
ソプラノ:隠岐 彩夏さん
アルト(カウンターテナー):藤木 大地さん
テノール:城 宏憲さん
バリトン:大西 宇宙さん
デスピノーサによる実演は、2014年5月にN響の定期演奏会に登場してフランクの交響曲やワーグナーのオペラ作品(マティアス・ゲルネが独唱)を採り上げたものを聴いていますが、その時の印象は何も残っていません。そのため、「真っ新の状態でデスピノーサの演奏ぶりに触れる」といった状態で、本日の第九に臨むこととなりました。
イタリア人ながら、2003年~08年までシュターツカペレ・ドレスデン(SKD)のコンサートマスターを務めていたというデスピノーサ。その当時の音楽監督であった同郷のルイージに勧められて、指揮者に転身したようです。SKDのコンサートマスターを務めていたということから、清々しいながらもコクのある音楽を奏で上げてくれそうな、そんな予感を抱いたものでした。
独唱陣では、まずは、アルトのパートを歌うカウンターテナーの藤木さんが注目であります。この1年ちょっとの間で何度か藤木さんの実演に接していますが、妖艶であり、かつ、男女の差を超越した中性的な味わいを音楽にもたらしてくれる、といった印象を持っています。本日の第九では、どのような歌を聞かせてくれるのか、とても楽しみでありました。
また、バリトンの大西さんには持ち前の、艶やかにして、朗々たる歌を聞かせてくれるのであろうことを期待しながら、席に着いたものでした。
ちなみに、今日も明日も、チケットは完売しているようです。そのこともあって、ホール内ロビーはいつも以上に多くの人で賑わっているようでした。更には、開演を待っている聴衆の多くは、年末の第九演奏会にウキウキとした気分を漂わせていたようにも感じられたものでした。
それでは、本日の演奏会をどのように聴いたのかについて、書いてゆくことに致します。

しやはや、デスピノーサ、素晴らしかったです。SKDのコンマスを務めていたという経歴から想像した通りの、清新にして音楽センスの豊かさを感じ取ることのできる演奏ぶりでありました。
情に流されるようなことがなく、キビキビと、そして、見通し良く音楽は進められる。音楽がもたれるようなことは殆どない。第1楽章の至る所で現れる、リタルダンドを掛けた後に元のテンポに戻る箇所なども、リタルダンドの余韻に浸るようなことをせずにテキパキと音楽を進めてゆく。その様は、実に気風の良いものでありました。
(第2楽章でダ・カーポする直前で、テンポを恣意的に緩めたのが、少し気になったくらいでした。また、最終楽章では、その前の3つの楽章では見せなかった、見栄を切るような表現がところどころで現れたのですが、それは、作品が要求している表情として、私は受け入れることができた。)
そのようなこともあって、とても短く感じられました。例えば、第3楽章では「えっ、もうあのホルンソロまで来ちゃったの!?」とか、最終楽章では、「えっ、もうトルコマーチに来たの!?」といった塩梅。確かに、テンポはやや速めでありました。しかし、ただそれだけではなく、音楽が毅然として進められていて、ダレるようなことが殆どなく、音楽が整然と、かつ、無駄なく流れていたが故の印象であったと言いたい。
しかも、やるべきことをシッカリとやり尽くしてくれていた。また、音価を大事にしていて、充実度の高い演奏を繰り広げてくれていました。例えば、曲が始まってまもない箇所になりますが、21小節目からの付点8分音符と16分休符とが組み合わされた動きなどでは、付点8分音符の音価分の長さがキッチリと保たれていつつも、8分休符がキチンと見えてくるように演奏されていた。そのようなことを誠実に実行しながら、演奏を積み重ねていく、そんな演奏が展開されていったのだと言いたい。
更に言えば、第1楽章の展開部の真ん中辺りで、対位法的な動きを見せる箇所などでは、必要以上に厚ぼったい音楽にするようなことはなかったものの、それぞれの楽器が分離良く、かつ、対等に鳴らされていて、音楽に充実感がもたらされていた。
また、、第2楽章では、推進力豊かに進められていき、かつ、躍動感や弾力性にも富んでいて、93小節目からの木管楽器群が束になって旋律を奏でる箇所などは、音楽が軽やかに飛び跳ねていた。その一方で、61小節目からのベートーヴェンが1小節ごと念入りにフォルテ記号を書き続けた箇所などでは、剛毅な音楽を奏で上げていった。
なお、これはデスピノーサが見せた「いたずら」なのですが、第2楽章の最後の一音だけを、音楽を飲み込むようにして、音をすぼめて終えたのには驚かされました。あまりに恣意的な処置だったのですが、他の箇所で誠実に音楽を奏で上げてくれていただけに、この「いたずら」が、何とも言えない妙味を生んでいました。
そのような中でも、第3楽章は、デスピノーサの音楽性が最大限に生かされていたのではなかったでしょうか。実に流麗な演奏となっていました。全く粘れるようなことはなかったものの、抒情的な美しさを湛えていました。更には、爽やかな歌謡性、といったものが感じられたものでした。天国的に美しく、しかも、敬虔な気分が横溢している楽章ではありますが、下手をするとまどろっこしさを覚えかねないこの楽章を、スッキリと、そして、格調高く演奏してくれていたのでありました。この楽章ならではの雅趣に富んでもいた。
このように書いてゆくとキリがありませんが、細かな箇所の例示は、これを最後にしたいと思います。それは、冒頭部分。あまり霧のかかったような音楽にはならずに、その中で奏で上げられるヴァイオリンによる旋律がクッキリと浮かび上がっていて、「晴朗な第九」になるであろうことを予感させるに十分な演奏ぶりでありました。
なお、最終楽章もまた、頗る見通しが良い演奏が繰り広げられていました。それでいて、十分な昂揚感を持っていた。変に勿体ぶるようなことが見受けられなかったのも、とても有難かった。
ちなみに、弦楽器は対向配置が採されていました。但し、それ故の特別な効果といったものは、あまり感じられなかった。
また、トランペットとティンパニが右手奥のほう(通常、コントラバスが位置している辺り)に陣取って演奏していて、音の粒がクッキリとしていて、音楽にアクセントを与えるに十分な活躍をしてくれていたのが印象的でした。本日の演奏は、総じて目鼻立ちのクッキリとしたものだったと言えましょうが、トランペットとティンパニの貢献度が高かったように思えます。
独唱陣は、可もなく不可もなく、といったところでしょうか。
冒頭の大西さんは、高らかに歌い上げてくれていたのですが、音程が定まっていなかったのが残念でした。
また、アルトパートは、あまり目立たないため、藤木さんの起用があまり効果的ではなかったように思えました。最後の箇所での4人の独唱者が順にカデンツ風に歌い上げる箇所でも、あまり表に出てくるといった感じになっていなかった。途中、ほんの僅か、藤木さんならではの妖艶さが音の重なりの中からチラッと顔を覗かせてくれたようにも思えたのですが。
なお、これは余談になりますが、独唱パートを歌い終えた後も、独唱陣は椅子に座ることなく合唱と一緒になって歌っていたのは、見ていて気持ちが良かった。また、独唱陣も合唱も、楽譜を持たずに暗譜で歌っていたのも、印象的でありました。
縷々書いてきましたが、デスピノーサの音楽センスの良さや、音楽への誠実さが光った、素敵な演奏でありました。
清々しさを湛えつつ、聴き応え十分な第九を聴いた、という満足感を抱くことのできながら、会場を後にしたものでした。