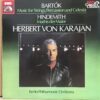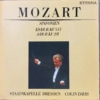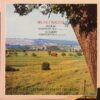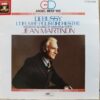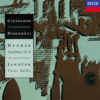パーヴォ・ヤルヴィ&エストニア国立響によるショスタコーヴィチの≪森の歌≫を聴いて
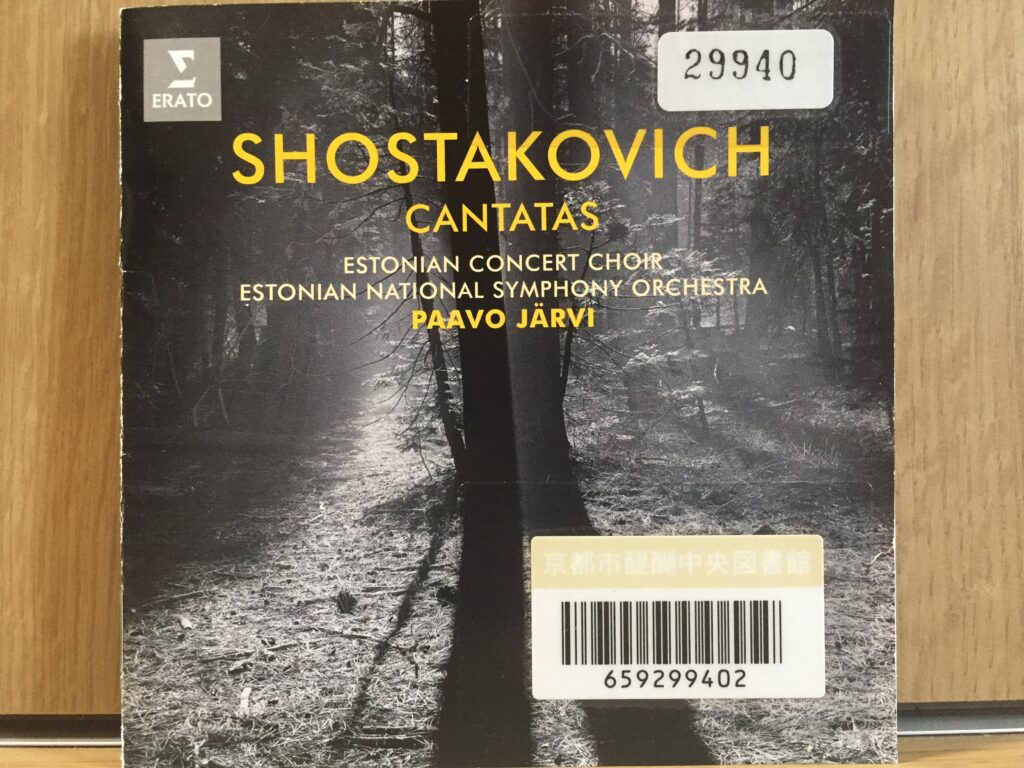
パーヴォ・ヤルヴィ&エストニア国立響によるショスタコーヴィチの≪森の歌≫(2012年録音)を聴いてみました。
図書館で借りてきたCDでの鑑賞。
エストニアの首都であるタリンに生まれたパーヴォは、母国のオーケストラとも密接な関係を保っていて、2002年からエストニア国立響の芸術顧問を務めています。同楽団とは、1990年代からシベリウスの管弦楽曲集や、グリーグの管弦楽曲集などを録音しています。また、パーヴォが開始したパルヌ音楽祭をきっかけに、2011年には、地元エストニアの優れた奏者やヨーロッパ各地のメジャー・オーケストラから奏者を選抜して編成されるエストニア祝祭管を創設してもいます。
この作品は、スターリンによる自然改造計画のなかの大植林事業を讃えるオラトリオ。平明で、親しみやすい音楽となっています。しかしながら、ショスタコーヴィチ本人は、旧ソ連政府に迎合する態度を示すことになったこの作品に対して、不本意な思いを抱いていたようです。
そのような≪森の歌≫を、パーヴォは、明快かつ力強く奏で上げています。テキパキとした音楽運びが為されていて、快活で、晴れやか。最終曲を筆頭に、誠に輝かしくもある。
パーヴォらしい、エッジの効いている、克明にして巧緻な演奏ぶり。鮮烈で、ドラマティックでもあります。そして、頗る逞しい。そのような演奏ぶりは、硬派タイプだとも言えそうですが、直球勝負が貫かれていて、難しいことを一切考えることなく、この作品の音楽世界に身を置くことができる。そのことによって、この平明な作品が、クリアな形で、より一層親しみやすく耳に入ってくる。
聴いていて痛快な気分にさせてくれる、見事な、そして、素敵な演奏であります。