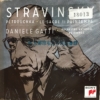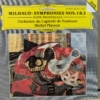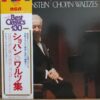ラナ&ネゼ=セガン&ヨーロッパ室内管によるシューマンのピアノ協奏曲を聴いて

ラナ&ネゼ=セガン&ヨーロッパ室内管によるシューマンのピアノ協奏曲(2022年録音)を聴いてみました。
NML(ナクソス・ミュージック・ライブラリー)に収蔵されている音盤での鑑賞になります。
ラナの実演は、1度だけ接したことがあります。それは、2017年4月のN響の定期演奏会でのことで、ベートーヴェンのピアノ協奏曲第1番を弾いた、というもの。指揮者はルイージでありました。
その時のラナの演奏ぶりについて、フェイスブックに次のように寄せています。
名前を聞くのも私は初めてのピアニストなのですが、逸材だと思います。プログラムに「豊穣な情趣と歌心、知性的な統制と機知をもつ期待の新星」と紹介されていますが、まさにその通りの音楽的な資質を持つピアニストであると感じました。
まずは音が美しい。そして、ニュアンスが豊か。音楽を作る際の「押したり引いたり」が絶妙。基本的には繊細な感性で音楽を感じて、それを現実の音に置き換えてゆく。それは「知的な統制」そのもの。
表情は千変万化し、押し付けがましさは一切ないのに雄弁で、サラリとした「濃密さ」(矛盾した言葉ですが、全くベタついていない濃密な世界がそこにあったのです)がある。全てが、感受性の豊かさに裏打ちされた音楽となっていたのでありました。
さて、当盤でのシューマンのピアノ協奏曲の演奏もまた、上記のことが当てはまりましょう。「知的な統制」によって奏で上げられている音楽となっている。そして、豊かな感受性に裏打ちされた音楽が鳴り響いている。
そのために、抒情性に溢れた音楽が鳴り響くこととなっています。ニュアンスが、とても細やかでもある。しかも、身のこなしが頗るしなやか。
更には、繊細にして、内省的な演奏ぶりだとも言えましょう。第1楽章での再現部に入ったばかりの箇所などは、その最たるものだと言いたい。
その一方で、曲想に応じては、音楽が奔流となって力強く推し進められてゆく。十分に律動的でもある。とは言いましても、過激なまでに荒れ狂ったり、情念的に過ぎたりといったようなことはなく、シッカリとした自制心が働いています。それ故に、音楽のフォルムが崩れるようなことがない。
そんなこんなによって、シューマンならではのロマンティシズムが、折り目正しくも、詩情豊か形で表出されています。
そのようなラナの演奏ぶりに対して、ネゼ=セガンもまた、鋭敏にして、精細な演奏を繰り広げてくれています。こちらもまた、感受性豊かな演奏ぶりだと言いたい。しかも、室内オケを起用しているが故に、カロリーオーバーするようなことは皆無で、キリっと引き締まった演奏となってもいる。
ラナとネゼ=セガンの魅力を存分に味わうことのできる、素敵な演奏であります。
なお、カップリングされている作品は、クララ・シューマンのピアノ協奏曲第1番。シューマン夫妻によるピアノ協奏曲を一挙に聴くことができるという企画は、なかなかに秀逸だと言えましょう。
こちらでも、繊細にして抒情性に満ちた演奏が繰り広げられています。更には、最終楽章での演奏では、夫のロベルトによる協奏曲での演奏ではあまり見られなかった情念的な表情が見受けられたのが興味深かった。