バックハウス&フリッチャイ&スイス・ロマンド管によるベートーヴェンのピアノ協奏曲第4番を聴いて
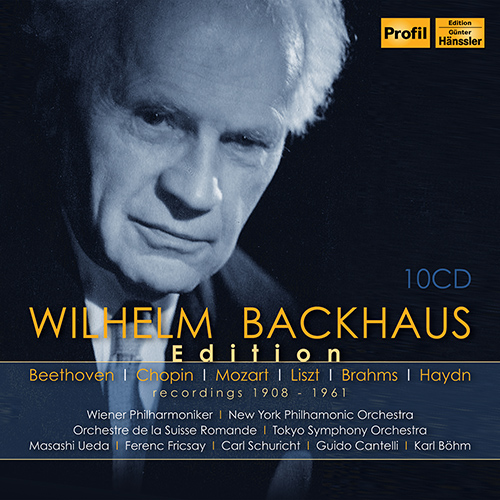
バックハウス&フリッチャイ&スイス・ロマンド管によるベートーヴェンのピアノ協奏曲第4番(1961/5/24 モントルーでのライヴ)を聴いてみました。
NML(ナクソス・ミュージック・ライブラリー)に収蔵されている音源での鑑賞になります。
気丈にして、剛毅な演奏であります。このことは、バックハウスにもフリッチャイにも当てはまる。そのために、女王と呼びたくなるような優美で気高い曲想を備えているこの作品が、男性的で猛々しく奏で上げられている。
バックハウスによるピアノは、ここでも、毅然としています。そして、タッチは強靭。このことは特に、急速楽章であります両端楽章において顕著。その一方で、第2楽章は、優しさに満ちていて、メランコリックに奏で上げられている。その振り幅は誠に大きい。それだけに、両端楽章での勇壮な性格が一層色濃くなっている。そのうえで、最終楽章では、歓びが弾けるような朗らかさを併せ持つ演奏ぶりが展開されている。
そのようなバックハウスに対して、フリッチャイによる音楽づくりは、全編を通じて勇ましさが前面に押し出されています。そう、第2楽章においても、オーケストラは荒れ狂っている。そのために、第2楽章ではバックハウスが見せてくれている優しさが引き立つこととなっている。
(第2楽章は、オーケストラを荒々しい猛獣に喩え、ピアノをそのような猛獣をなだめるかのように応答する、といった捉え方ができるという話を、以前どこかで聞いたことがあります。)
フリッチャイによるベートーヴェンのピアノ協奏曲のセッション録音は、アニー・フィッシャーとの第3番が残されているのみで、あとは、ライヴ録音が幾つか存在する、といったところのはず。その意味でも、この録音は、とても貴重だと言えましょう。しかも、共演者がバックハウスというところが、その存在意義を大きくしてくれている。と言いつつも、そのようなことに拘らなくとも、ここでのフリッチャイによる演奏は、実に説得力の大きなものになっていると思えます。
なお、ここでのスイス・ロマンド管の響きは、誠に重厚。アンセルメによる演奏で聞かせてくれる、色彩的でありつつも、硬質で玲瓏である響きとは、一線を画すものとなっています。
バックハウスとフリッチャイとが、がっぷりと組み合った、しかも、随所で丁々発止のやり取りを見せてもくれる演奏。それはまさに、一期一会のものと言えましょう。
協奏曲を聴く醍醐味を存分に味わうことのできる、見事な、そして、頗る魅力的な演奏であります。
ちなみに、最終楽章のカデンツァは、バックハウスの自作のもの(イッセルシュテットとのセッション録音で使用されたものと同じ)が使われていました。






