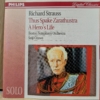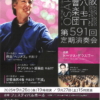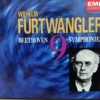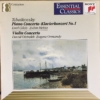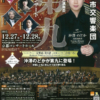山下一史さん&大阪交響楽団による演奏会(ヴェルディの≪レクイエム≫)を聴いて

今日は、山下一史さん&大阪交響楽団の演奏会を聴いてきました。演目は、ヴェルディの≪レクイエム≫。
独唱は、森谷真理さん(S)、林美智子さん(MS)、笛田博昭さん(T)、伊藤貴之さん(Bs)という陣容。
山下さん&大阪交響楽団のコンビは、昨年にオール・ブラームス・プロを聴き、今年の4月にはモーツァルトのディヴェルティメントとセレナードを並べたプログラムを聴いていまして、ともに強い感銘を受けたものでした。そのような中で、前2回とは全く性格の異なる作品となるヴェルディの≪レクイエム≫で、どのような演奏を繰り広げてくれるのか。なんとも興味深いところでありました。
また、独唱陣も充実しています。とりわけ、テノールの笛田さんに大注目。ここ1年ほどの間に、≪蝶々夫人≫のピンカートン、≪運命の力≫のドン・アルヴァーロで、輝かしい歌声を聞かせてくれているだけに、今日もまた、私を痺れさせてくれるであろうと、心ときめかせながら会場に向かったものでした。
なお、今回の演奏会は「創立45周年記念」と銘打たれています。大阪交響楽団が創立されて45周年になることを記念しての演奏会。
しかも、本日の9月28日は、このオケの創立記念日だとのこと。と言いますのも、創設者の故敷島博子氏の誕生日が9月28日のため、この日を創立記念日としている旨が、プレトークで説明されました。
敷島氏は、若者たちが音楽で生計を立てることは困難なことで、自身が所属されていたアマチュア合唱団の伴奏をするオーケストラを創ることで若者たちの窮状を救えるのではないかと考え、このオケを設立されたのだそうです。そのため、設立当初は合唱を含む作品を数多く演奏していたという歴史を持っているとのこと。そのようなな背景もあって、創立記念公演にヴェルディの≪レクイエム≫を採り上げたとのことでありました。
それでは、本日の演奏会をどのように聴いたのかについて、書いてゆくことに致しましょう。

なんとも素晴らしい演奏でありました。山下さんがヴェルディの音楽を、こんなにも雄弁に、そして、生気を帯びた形で演奏を繰り広げてくれるとは、驚きでありました。山下さん、暗譜で指揮をされていました。そのことが物語っているように、この作品を完全に掌中に収めておられるのでしょう。
しかも、オケと合唱陣を存分に鳴らし切りながら、頗る壮麗な音楽を奏で上げてくれていた。弦楽器群のプルトの数は7-6-5-4-3と、この作品を演奏するには各パートをもう1プルトずつ増やしても良いのでは、といったところではありましょうが、このプルト数でも、輝かしくて、豊かな響きを獲得していました。それは、山下さんのオケをドライブする巧みさ故だったのでありましょうし、大阪交響楽団が献身的に応えてくれていた賜物でもあったと言えましょう。プレトークで、山下さんはこのオケのシェフに就任して4シーズン目になり、自分の志向する音楽を理解してくれる団員も随分増えていると仰っていましたが、そのような蜜月ぶりが反映された結果でもあるのでしょう。
そのようなこともあって、この大規模な作品を充実したものとして鳴り響かせていました。作品との間に、齟齬をきたすようなところが微塵も見受けられなかった。そして、頗る逞しい息遣いをした音楽が鳴り響いていた。
しかも、大袈裟であったり、変に芝居じみていたり、といったところが、これっぽっちもなかった。まさに、ケレン味のない音楽づくりが為されていたのであります。もっと言えば、この作品の真髄に迫ろうとする、ただそれだけのために演奏していたようにも思えてならなかった。その結果として、気宇が大きくて、なおかつ、お祭り騒ぎにならない敬虔な音楽世界が広がっていったのであります。
それでいて、十分にドラマティックだった。激情的でもあった。音楽が至る所でうねっていた。これらは、まさにこの作品の真髄の一つでもあり、そのような性格を余すところなく描き切っていたと言いたい。
更には、音楽が弛緩するようなことも一切なく、緊迫感に満ちた音楽が奏で上げられていた。
そんなこんなも、山下さんの音楽性の豊かさと、音楽への誠実さ故なのでありましょう。
独唱陣も、おしなべて見事でありました。とりわけ、開演前から注目していた笛田さんには惚れ惚れとしたものでした。
笛田さんの歌いぶりは、頗る強靭であり、ドラマティックなものでありました。中低音部が暗めの色調になるのは、生粋のドラマティコである証だと言えましょう。バリトンのような声音をしていて、それを高音部へと持ち上げることによって、声に独特のハリが生まれ、陽が燦々と降り注ぐような輝かしさが備わることとなる。そんな笛田さんによる歌唱は、声を聴く歓びに満ちたものだったと言いたい。
また、バスの伊藤さんも、実に立派でありました。その歌いぶりは、バッソ・プロフォンド(威厳のあるバス歌手)と呼ぶに相応しいものでした。気品がありつつ、艶もあって、そのうえで、押し出しのシッカリとした歌唱を繰り広げてくれていました。
初めて聴いたバス歌手かと思っていましたが、2022年11月に、びわ湖ホールで上演された≪セヴィリャの理髪師≫でのドン・バジーリオを聴いていたようです。そこでの印象として、「声と歌いぶりに太さと拡がり感があり、かつ、深々としていて、この役に相応しい歌であったと思います」と書いていました。伊藤さん、もっともっと聴いてみたい歌手であります。
ソプラノの森谷さんは、実にリリカルなものでありました。
ここ2年半ほどの間、びわ湖ホールで、≪ニュルンベルクのマイスタージンガー≫のエヴァ、≪こうもり≫のロザリンデ、≪死の都≫のマリーとマリエッタの2役と、彼女の実演に触れる機会に3回恵まれていますが、それらの歌唱においては、ドラマティックな歌いぶりを示すソプラノだ、という印象を強く抱いたものでした。どちらかと言えば、猛女系のソプラノだと思えたのでしたが、その正反対と言えるような歌いぶりだった。
全体的に清潔感に満ちていて、なおかつ、凛としてもいて、心に沁み渡るような歌を聞かせてくれたものでした。そのような中、終曲の「リベラ・メ」での“Requiem, requiem”と弱音で高音に上がる箇所(167-170小節目)の最後の小節で、ppppでオクターヴ上のB♭を歌い上げる箇所で、安全策で声を強めてしまっていたのが興醒めでありました。この箇所を、ppppで清澄な声を聞かせてくれていたならば、森谷さんの歌唱全体の感銘はグンと上がっていたことでありましょう。
メゾ・ソプラノの林さんは、これまでは、可憐なお嬢様系といったイメージを持っていただけに、思いのほか凄みを効かせた歌いぶりになっていたのには驚かされました。音楽をグイッと抉るような歌になってもいた。その一方で、時に不安定さが顔を覗かせていたのが、ちょっと残念でもありました。とは言うものの、この作品はメゾ・ソプラノが4人の独唱陣の先陣を切る場面が多いといった、重要な役回りを担っており、性格的な歌唱が求められるだけに、そういった役割をそつなくこなしていたとも言え、なかなかに魅力的な歌唱だったと思います。
合唱は、十分に力強いものでありました。昂揚感があり、細やかなニュアンス付けが施されてもいた。本日の演奏を魅力的なものにしてくれていたことへの貢献は、とても大きかったと言いたい。
かように、全体的に、とてもレヴェルの高いヴェルディの≪レクイエム≫だったと思えましたが、やはり、山下さんによる統率と、音楽づくりとが、本日の演奏を聴き応え十分にしてくれたことの筆頭に挙げたい。正直言って、それは、ちょっと思いがけないほどのものでもあった。
満ち足りた気分で、会場を後にしたものでした。