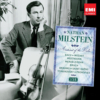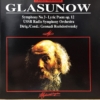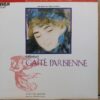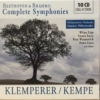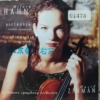ヘブラー&ロヴィツキ&ロンドン響によるモーツァルトのピアノ協奏曲第9番≪ジュノム≫を聴いて

ヘブラーによるモーツァルトのピアノ協奏曲全集から第9番≪ジュノム≫(1968年録音)を聴いてみました。
この全集では、コリン・デイヴィスやガリエラなど3人の指揮者がロンドン響を指揮してヘブラーをバックアップしており、この作品で指揮をしているのはロヴィツキ。
この作品は、ピアノ協奏曲としては1桁台の番号となっているために、初期の作品だと思われるかもしれませんが、モーツァルトが21歳の時に作曲された中期の作品になります。ケッヘル番号は271。交響曲で言えば、第30番までが既に完成されている。
モーツァルトのピアノ協奏曲は、第20番以降に人気が集中していると言えましょう。しかしながら、10番台にも魅力的な作品が多く、更に遡って、第9番の≪ジュノム≫もまた、実にチャーミングな佳品であります。私の大好きな作品の一つ。
その魅力はと言えば、飾り気のない可憐さにあると言えば良いでしょうか。両端の急速楽章では、軽やかにして精妙で、かつ、優美な音楽世界が広がってゆく。その一方で、緩徐楽章となる第2楽章は、深奥な音楽となっている。
さて、ここでのヘブラーの演奏は、そんな≪ジュノム≫の魅力を、ストレートに味わうことのできる演奏となっています。なんの虚飾もない、純美な音楽が奏でられている。柔らかみや、暖かみや、優しさを湛えてもいる。
そのうえで、気品があって、優美でもある。しかも、音の粒が揃っていて、かつ、まろやかな響きがしており、端正な音楽が鳴り響いています。必要以上に運動性を強調している訳ではないのですが、十分に溌剌としていて、飛翔感にも不足はない。
自然体な演奏であり、とても清楚でもある。もっと言えば、無垢な音楽が奏で上げられている。
作品に対しても、演奏に対しても、「あ~、なんと素敵な音楽なのだろう」という感慨が湧いてくる、頗る魅力的な演奏であります。