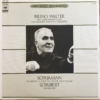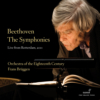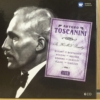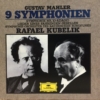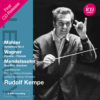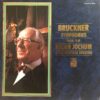高関健さん&京都市交響楽団による演奏会(マーラーの交響曲第5番 他)の第2日目を聴いて

今日は、高関健さん&京都市交響楽団による演奏会の第2日目を聴いてきました。演目は、下記の2曲。
●カーゲル ティンパニ協奏曲(独奏:中山航介さん)
●マーラー 交響曲第5番
高関さんによる実演は、1989年に≪魔笛≫全曲を聴いて以来でしょうか。大学オケに所属していた当時、木管セクションのトレーナーを務めて頂いていた方が、この公演でピットに入った新星日響の団員だったこともあって、聴きに行ったのでした。
高関さんは、2019年のシーズンまで京響の常任首席客演指揮者を務めておられたようですが、それ以降は、コロナ禍で来日ができなくなった指揮者に代わって2021年1月の定期演奏会を指揮したのみのよう。その演奏会は聴きに行けていませんので、高関さん&京響のコンビによる演奏に触れるのは、今回が初めてになります。
今年70歳になられている高関さんですが、首都圏に在住の知人から、群馬交響楽団や東京シティ・フィルなどで聴き応えのある演奏を度々聞かせてくれているという話が伝わってきていまして、とても気になる存在でありました。そんな高関さんの「現在」に触れることができる、本日の演奏会。どのような演奏に巡り会うことができることだろうかと、期待を膨らませながら会場に向かったものでした。
なお、前プロのティンパニ協奏曲を作曲したカーゲル(1931-2008)は、アルゼンチンの生まれで、1957年に西ドイツのケルンに移って逝去するまで同地に暮らしたとのこと。名前を聞くのも初めての作曲家でありますが、プログラム冊子には、「しばしば演奏者に演劇的なしぐさを求めることが特徴となっている」と書かれています。
その中でも、指揮者が突然苦しみだして倒れる(という指示のある)≪フィナーレ≫と、本日演奏されるティンパニ協奏曲が、特によく知られているとのこと。と言いますのも、この協奏曲の最後の箇所には、ティンパニ奏者がティンパニに上半身を突っ込む、と指示されているが故に。
そのような協奏曲でソリストを務めるのは、京響の首席打楽器奏者の中山さん。
そんなこんなをプログラム冊子で知り、興味を掻き立てられながら客席に着いたものでした。
それでは、本日の演奏会をどのように聴いたのかについて書いてゆくことに致しましょう。

まずは前半のティンパニ協奏曲から。
硬めのバチや、柔らかいバチや、更にはバスドラを叩くのに好都合と思われるような頭の大きなバチが使われたり、また、頻繁に素手で叩いたり、或いは、リムショットをしてみたりと、多様な奏法が組み込まれていて、そこから生まれる響きの多様性を楽しむような音楽になっていました。また、途中には、ティンパニ独奏者がメガホンを持ってくぐもった響きで歌を歌ったりといったシーンもあり、多彩な趣向が施されていました。
そのような独奏ティンパニに対して、オケもまた多様な響きを鳴り響かせながら、ソリストを包みこんでゆく、といった音楽になっていた。そのオケがまた、頗る色彩的でもあった。
音楽の進行は、ソリストが主体性を持って進めてゆくというよりも、指揮者がリードしてゆく、といった要素が強かったようにも思えました。そのような作品に対して、高関さんが、キッチリとした指揮ぶりで、見事に全体を統率していたように感じられたものでした。そう、その指揮の動きは、とても明快で、音楽がどのように進もうとしているのかが、手に取るように理解できた。
プレトークでの話ぶりも含めて、高関さん、かなり律儀で、誠実な方のように思えたものでした。
最後には、目まぐるしく5台のティンパニを叩き分けながら乱打しながらクライマックスを迎えたのですが、その様は壮絶であり、圧巻でありました。また、ティンパニに上半身を突っ込んで終わると、会場からは笑いが漏れていました。そんな、笑いも取れる作品でありました。
なお、終演して、大ホールを出て回廊を降りてくると、ソリストが上半身を突っ込んで破いてしまったティンパニが展示されていましたので、写真撮影してきました。ちなみに、張られているのは皮ではなく紙であります。
このような展示を行うとは、洒落が効いていますよね。

さて、それではここからは、メインのマーラーについてであります。それはもう、期待を上回る、素晴らしい演奏でありました。
プレトークで高関さんは、マーラーはこの交響曲を再三に渡って書き換えていて、死の直前にも校訂を行なっていたことと、その校訂版をニューヨーク・フィルで演奏する前に、この世を去ったことを紹介していました。その校訂とは、小節を加えたり削ったりするようなことは一切せずに、アーティキュレーションを変更したり、オーケストレーションの変更なのでしょうか響きがよりクリアになることを目的にしたり、といったようなことだったとのこと。その「最終版」はつい最近になって出版される運びとなり(それらの変更は、フルスコアのみに加えられていたり、パート譜のみに施されていたりと、複雑な様相を呈しているようです)、その版をいち早く取り寄せて、今回の演奏に用いるようにしたそうです。
その説明は、頗る丁寧であり、かつ、極力整然と聞かせていこう、といった配慮が感じられたものでした。とは言うものの、どこの箇所にどのような変更が為された、といった些事には一切触れていなかった。触れ始めたら、キリがないのでしょう。校訂へのマーラー本人の意図やコンセプトと、その過程について、丁寧に説明された、といったものでした。
本日の演奏に接した第一印象は、そのような高関さんの姿勢がクッキリと現れていた演奏だった、というものでした。すなわち、とても明晰で、目鼻立ちのクッキリとした演奏が展開されていた。そのような演奏を目指すことがマーラーの意図を汲むことになるのだ、といった高関さんの意志を感じ取ることができた。
そのうえで、息遣いが頗る自然だった。ここは、ダレることなく前へ前へと前進して欲しい、と望む箇所では、決然とした態度で前進させていった。ここはシッカリと溜めて欲しい、という箇所では、深い呼吸を伴いながら音楽は奏で上げられていった。そのような呼吸感が絶妙であり、かつ、曲想に適ったものだったように思えてならなかった。しかも、うねりを上げながら驀進して欲しい箇所は、音楽が存分にうねっていた。
そんなこんなによって、活力が漲っていて、生命力に溢れた音楽が鳴り響くこととなっていたのであります。しかも、少しも誇張されることがなく。
なんと逞しくて、かつ、しなやかな演奏だったことでしょう。そこには、高関さんの音楽への誠実さが如実に感じ取れたとともに、音楽センスの高さが伝わってきたものでした。
また、第4楽章では、清らかにして、甘美な音楽世界が広がっていた。しかも、ここでも音楽がダレるようなことはなかった。
更には、冒頭のトランペットによるソロは、毅然としていつつも、硬質でありつつも、柔らかさをも伴っている音楽が奏で上げられていた。
そのような中で、個人的に頂けなかったのは、第3楽章でのホルンのソロ。この楽章のみ、1番ホルン奏者を指揮者の横(コンマスの前)に立たせて、ソリストとして振る舞わせていたのですが、6小節目に記されているfpの指示を過剰に強調させていて(このfpは、8小節目、18小節目と、その後も何度も何度も現れる)、実に凶暴な吹き方になっていた。音楽をぶち壊すような強調ぶりでもあった。この楽章の諧謔味を強調しようとしたのでしょうが、諧謔的であるというよりも、攻撃的に過ぎていた。
しかも、音を随所で押していく。その様が、実に下品に感じられたものでした。また、強音では音がスコーンと抜けてこなくて、一度楽器の中の何処かで音が引っかかった上で、楽器の外に出てくる、といった感じになっていた。更には、音が上ずっているような印象を与えることが多かった。これは、変に力み過ぎていたからでしょうか。
そのような演奏ぶりが、指揮者の横に立ちながらの演奏だったということによって、かなり助長されていたようにも思えた。
この楽章のホルンソロは、私には拷問のようでした。早くこの楽章が終わって欲しい。そんな思いで聴いていたものでした。
かように、ホルンソロには閉口したものの、総じて聴き応え十分なマーラーの5番でありました。首都圏在住の知人が、高関さんを高く買っておられることが、よく理解できた演奏でもあった。
十分なる満足感を抱きながら、会場を後にしたものでした。