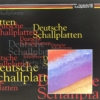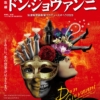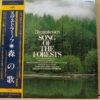プレトニョフ&兵庫芸術文化センター管による演奏会(オール・チャイコフスキー・プロ)の最終日を聴いて

今日は、プレトニョフ&兵庫芸術文化センター管(通称:PACオケ)による演奏会を聴いてきました。演目は、下記の2曲。
●チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲(独奏:前田妃奈さん)
●チャイコフスキー ≪白鳥の湖≫(プレトニョフによる特別編集版)
今年68歳になった、ロシア生まれのピアニスト兼指揮者のプレトニョフ。そんなプレトニョフによるオール・チャイコフスキー・プロという、魅力的な演奏会であります。メインの≪白鳥の湖≫抜粋は、プレトニョフによって選曲・編集されたもの。なお、プレトニョフがPACオケを指揮するのは、これが初めてのようです。
また、ヴァイオリン独奏として2022年のヴィエニャフスキ・コンクールで優勝した前田妃奈さんが登場することにも注目。
プレトニョフによる演奏は、力感に富んでいて強靭で、しかも、磨き上げが丹念で粗さがない、といった印象を持っています。表現意欲が旺盛でありつつも、洗練味を帯びている。
本日のチャイコフスキーでは、どのような演奏を繰り広げてくれることだろうか。期待に胸を膨らませながら会場に向かいました。
それでは、本日の演奏会をどのように聴いたのかについて書いてゆくことに致しましょう。

まずは、前半のヴァイオリン協奏曲について。
前田さん、期待外れでありました。情熱家なのでしょうが、音楽が空転していると思えたものでした。
第1楽章は、概してゆっくり目のテンポで、情感を籠めて弾いてゆく、といった演奏ぶり。濃密で、かつ、激情的な演奏でありました。
しかしながら、音楽が自然に流れていかない。そう、淀みながら進んでゆく、といった感じ。それ故に、聴いていてもどかしい。
そのような前田さんの演奏ぶりに対して、プレトニョフは、醒めた感じで音楽を付けてゆく。
独奏ヴァイオリンを伴わない箇所では、雄弁な音楽を奏で上げていました。例えば、主題提示部が終わってオケだけで壮麗に奏で上げてゆく箇所などは、タップリとした音楽が鳴り響いていた。また、曲が始まってまもなくの箇所で、第1ヴァイオリンにアタックを付けさせながらも野太い音を引き出していて、彫りの深さを施していた。
それでいて、ヴァイオリン独奏が入ってくると、事務的な対応をしてゆく、といった風だったのであります。プレトニョフ、前田さんのソロに感情移入できなかったのかな、などと勘ぐってしまいました。
そのような中でも、前田さんの演奏ぶりとしましては、第2楽章での瞑想的な演奏ぶりが曲想にマッチしていたと言えそう。プログラム冊子に掲載されていた前田さんへのインタビューの中で「実は第2楽章が1番得意です」と語っていたことが紹介されていますが、そのことがよく理解できた。但し、合いの手としてロングトーンを挟むホルンが、音が大き過ぎてデリカシーに欠けていて、前田さんの演奏を邪魔していたと思えてならず、興覚めでありました。その分、前田さんは損をしてしまっていたとも言いたい。
(本日のホルンのトップは、私が注目している宇名根さんではありませんでした。)
第3楽章のエンディングなどは、かなり激情的でありました。ここの箇所についても、インタビューで次のように語っておられました。
「3楽章はやはり最後がいいですよね。長い間奏では1楽章と違ってオーケストラが盛り上げてくれて、その時が1番ワクワクします。最後だ!という気持ち、終わってしまう寂しさ、気を抜くなという自戒が入り混じりますが、最高です。」
そのような言葉が頷ける、体当たり的な演奏で、これでもかこれでもかと、力をぶつけていく熱演ぶりだった。「何振り構わず」といった演奏ぶりで、赤裸々な情熱が籠められていた。それは、ちょっと暑苦し過ぎるのではないか、といった風でもあった。
その一方で、プレトニョフが率いるオケは、冷静沈着に演奏を進めてゆく。ソリストと、指揮者&オケとの間の温度差の凄まじさが凝縮されていたエンディングになっていて、言葉は悪いが、ちょっと滑稽でもありました。
終演後は、会場は湧きに湧いて”Brava”が飛び交っていましたが、私には、どうにも座りの悪い演奏だったというのが正直なところでありました。
ソリストアンコールは、マスネの≪タイスの瞑想曲≫。ハープが伴奏しながらの演奏が披露されました。
なんとも勿体ぶった演奏ぶりでありました。協奏曲の第2楽章での瞑想的な演奏ぶりを更に強調した演奏だったと言えば良いでしょうか。
大半を弱音で奏で上げていて、頗る儚げな演奏だった。なるほど、弱音による演奏は、ときに極めて雄弁な音楽を出現させてくれるのですが、ここでの前田さんによる演奏は、単に貧弱な音楽になっていたと言いたい。弱音による音楽世界を支え切れていなかったと思えてならなかったのです。
しかも、音楽が滑らかに流れていかない。
そんなこんなを含めて、人工的な匂いの強い音楽になっていた。もっと言えば、感じ切った演奏のようでいて、わざとらしさに満ちた演奏だと思えてならなかった。
かなり問題の多い演奏だった。私には、そんなふうに思えました。
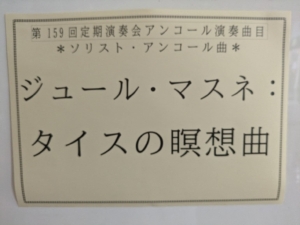
さて、ここからはメインの≪白鳥の湖≫についてであります。前半での鬱憤を晴らしてくれたと言いたくなるほどに素晴らしい演奏でありました。
プレトニョフの音楽づくりは、力み返ったところがない。強音部でも、力8分で奏で上げてゆく、といった感じ。それ故にと言いましょうか、音が混濁するようなことは一切ない。しかも、十分に豊麗な音楽が鳴り響いていました。バレエ音楽としての華麗な雰囲気も十二分であった。
組曲版のように、それぞれのナンバーが独立して奏でられる、といった構成になっておらずに、ストーリー性を保った上で進められてゆくことになっていた点も含めて、劇性の高い演奏だったと言えそう。そのことに付随することだと言えるのでしょうが、起伏に富んだ演奏が繰り広げられることとなってもいました。ドラマティックでありつつも、リリカルな味わいにも不足はなく、ロマンティックでもあった。しかも、そういった性格が、誇張なく示されてゆく。そう、劇性豊かであり、力感に富んでいて、なおかつ、端正で精妙な音楽が奏で上げられていたのであります。音楽に潤いがあった。艷やかでもあった。過剰に派手になるようなことはないものの、十分に色彩感に富んでいた。感傷的に過ぎるようなことがない中で、キリッとしたロマンティシズムを湛えていた。
そんなこんなを含めて、実に丹念な音楽が奏で上げられていたのであります。洗練味を帯びてもいた。こういった印象は、まさに、これまでに音盤で聴いてきたプレトニョフによる演奏の特徴そのもの。プレトニョフの真骨頂や、美質といったものが、遺憾なく発揮されていた≪白鳥の湖≫だった。そんなふうに言えるのではないでしょうか。
なお、前プロのヴァイオリン協奏曲も含めて、全て暗譜で指揮をしていました。両曲ともに、完全に手の内に収めているのでしょう。そのようなことが具現化されていた、息遣いの自然さが滲み出ていた演奏だったとも思えます。
また、オケの配置は対向配置が採られていました。これは、端正さを希求するが故のことなのでしょうか。ちなみに、本日の演奏を聴いていて、対向配置を採っていたからこその効果、といったことは、特に感じられはしませんでした。
さて、コンマスは豊嶋泰嗣さんが務めておられたのですが、コンマスソロ、見事でありました。前半の協奏曲での前田さんの演奏ぶりが頗る奔放なものであっただけに、豊嶋さんの凛としていて、かつ、端正なソロが、余計に印象的だったとも言いたい。また、チェロのトップは元東京交響楽団首席の西谷さんが務めておられたのですが、こちらのソロもまた、艷やかで滑らかな音楽を奏でてくれていて、素敵でした。両者のソロともに、優美な世界を現出してくれるものだったと言いたい。
かような演奏ぶりによって、約45分間の抜粋版でしたが、弛緩することなく奏で上げられていった、と言えましょう。そのうえで、≪白鳥の湖≫の魅力を存分に味わうことのできた、素敵な素敵な演奏でありました。