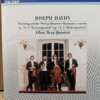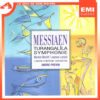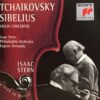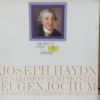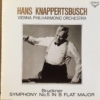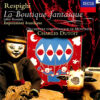ベルチャ弦楽四重奏団とエベーヌ弦楽四重奏団による合同演奏会(於:びわ湖ホール)を聴いて

今日は、びわ湖ホールで、ベルチャ弦楽四重奏団とエベーヌ弦楽四重奏団による合同演奏会を聴いてきました。演目は、下記の2曲。
●メンデルスゾーン 弦楽八重奏曲
●エネスク 弦楽八重奏曲
現代屈指のカルテットによる共演。しかも、メンデルスゾーンと、滅多に演奏されないエネスクによる弦楽八重奏曲を組合わせた興味深いプログラム。東京、神奈川に続いて、本日が3回目の公演になるようです。
世界的な弦楽四重奏団が組んでのメンデルスゾーンの八重奏曲と言えば、音盤では、スメタナ弦楽四重奏団+ヤナーチェク弦楽四重奏団や、スメタナ弦楽四重奏団+パノハ弦楽四重奏団によるものが思い出されますが、実演で接する機会は、なかなか無いのではないでしょうか。そのようなこともあって、実に楽しみな演奏会でありました。
それでは、この演奏会をどのように聴いたのかについて、書いてゆくことに致します。

まずは、前半のメンデルスゾーンから。いやはや、唖然とするほどに素晴らしい演奏でありました。
なお、エベーヌSQのメンバーが上の声部を弾いていました。並びは、左からスコアの段の通りに座っていた。そのために、最終楽章の冒頭は、ステージに向かって右手から順に左へ左へと、8分音符による、忙しくて、峻烈なパッセージが奏で上げらゆくことになっていた。
ところで、第1楽章の冒頭の第1ヴァイオリンによる旋律は、思いのほか、柔らかみを持ってデリケートに奏でられていました。楽譜にはcon fuoco(火が燃え滾るような情熱を持って)と書かれていますが、con fuocoな音楽と言うよりも、エレガントな音楽になっていた。それは、フランスの団体でありますエベーヌSQの体質が反映された結果なのかな、とも思ったものでした。
とは言いましても、この作品に不可欠な律動感には不足はありませんでした。必要十分にうねってもいた。しかも、緊密なアンサンブルに支えられながら、音楽が進んでゆく。そのうえで、瑞々しくて、凛とした音楽になっていた。
惚れ惚れしたのは、1番カッコ。この箇所の第1ヴァイオリンは、途轍もない高音域を駆け上がってゆくことになり、音程を取るのが非常に難しい。しかしながら、音程にブレはなかった。そのうえで、頗る艷やかな音を響かせていた。その美しさたるや、破格なものがありました。聴いていて、恍惚としてきた。この1番カッコを聴けただけでも、この演奏会に来た甲斐があった。そんなふうにも思ったものでした。
1番カッコでは、感覚的な興奮を存分に味わうことができたのですが、本日の第1楽章での白眉は、展開部の真ん中辺りだったでしょう。展開部に入ってしばらくの間は、熱量の大きな音楽が奏で上げられるのですが、その熱気が沈静化されていった後(練習番号Dの9小節前辺りから)、トランクィーロな雰囲気が支配的になります(楽譜には、特段、トランクィーロの表記はありません)。音楽が、儚げにして、たゆたうように進められてゆく。その表情の、なんと玄妙なことだったでしょう。この楽章は概して、情熱的で、勇壮で、輝かしくて、流麗な音楽となっているのですが、この箇所のみは、繊細な色合いを見せる。そのコントラストが鮮やかに付いている演奏となっていた。その精妙さに、聴いていて吸い込まれるようでもあった。その様は、練習番号Dで、第1ヴァイオリンと第1ヴィオラがユニゾンで呟くように音楽を奏でる箇所に入っても、続いた。その雰囲気を打破するように、シンコペーションのリズムを伴いながら、徐々に活気を取り戻していき、途中からは幾つかのパートによる16分音符によるパッセージを交え、最後には8つの楽器全てが16分音符でのパッセージを力強く奏で上げていき、再現部に突入する。その演奏ぶりもまた、頗る鮮やかなものでした。「なんと魅力的な音楽に、今、私は触れることができているのだろう」という思いが込み上げてもきた。
第2楽章での演奏は、第1楽章で「トランクィーロな雰囲気が支配的」と書いた箇所での演奏ぶりの延長線上にあったものだったと言えましょう。頗る精妙にして、玄妙なものになっていました。しかも、「たおやかな歌心」といったようなものが感じられもした。感情に溺れたりするようなことのない歌心。デリカシーを伴った歌心。そして、決してベトつくようなことのない歌心。そういったものが横溢していた。その様は、この楽章に誠に似つかわしいと思わずにはおれなかった。
第3楽章のスケルツォは、愁いを帯びていつつも、羽毛のように軽やかな(楽譜には、leggierissimoと書かれている)音楽であります。大気中を浮遊するような音楽となっている。メンデルスゾーンに特有の、妖精の音楽でもあります。それゆえに、ゴリゴリと弾いてゆくのはご法度。しかも、頗る機敏な音楽で、精度の高いアンサンブルが要求される。演奏難度のとても高い楽章だと言えましょう。下手をすると、音楽をぶち壊しかねない。繊細な演奏が求められる楽章でもある。
そのような第3楽章を、まさに水も漏らさぬアンサンブルと評したくなるような精密さで、奏で上げていった。16小節目からの8小節間では、短いパッセージを各声部が順繰りに弾いてゆくのですが、そこでの各奏者の機敏な反応などは、間然するところがなかった。そして、この楽章の全体を通じて、音の粒がクッキリとしたものとなっていた。それはもう、見事な第3楽章でありました。
その第3楽章からアタッカで最終楽章になだれ込んだのですが、速めのテンポを採りながら、怒涛の演奏が繰り広げられていった。快活などという表現が生ぬるく思えるほどの力感を備えていて、熱気に溢れていた。それはもう、目が眩むような音楽が展開されていったのであります。
しかも、決して粗くならない。唖然とするほどに精緻な音楽となっていた。ヒステリックになったり、音楽が硬直したり、といったことは一切なく、潤いがあって、弾力性を帯びていた。
しかも、頗る精妙でもあった。例えば、Cの17小節目からは、一つの旋律を1本の楽器が奏でるのではなく、1音ずつ、音を発する楽器を変えながら旋律が形成される(それは、4人のヴァイオリン奏者が順繰りに音を鳴らす、という形が採られている)ようになっています。その様は、あたかも「もぐら叩き」のもぐらが、頭をひょこっ、ひょこっと出してゆくよう(その頭を出すタイミングは、とても速い)でもある。そのことによって、1人で奏でる時とは異なる色合いが生まれてくるのですが、その演奏ぶりの、なんと精妙なことだったでしょうか。しかも、ここでも第3楽章での演奏と同様に、反応の機敏さが窺えた。メンデルスゾーンの施したトリックの妙味を、見事に再現してくれていたと言いたい。
また、最終楽章での演奏で印象的だったのは、練習番号Gの4小節目での第3ヴァイオリン(ベルチャSQの第1ヴァイオリンが担当)。第3楽章の素材が再現されている最中に現れるパッセージであります。この箇所では、第3ヴァイオリンのみにcon fuocoの指示が書かれているのでが、その演奏ぶりは、まさに火花が散ったかのような激烈さでありました。このような主張がシッカリと為されているということの、なんと尊いことでしょう。既に、熱く燃え滾るような演奏が展開されている中で、より一層のアグレッシブさで果敢に攻めていたのには、舌を巻いてしまいました。
演奏はそのまま、怒涛の勢いで突き進んでいき、唖然とするほどの昂揚感を築きながらクライマックスを迎える。聴いているこちらも、身体が火照ってきてならなかった。
そのあまりに壮絶な演奏ぶりに、聴いている途中でむせてしまいました。唾液を飲み込もうした際に、うまく飲み込めなかったのであります。このような経験は、これまでにありません。
圧倒的な感銘をもたらしてくれた演奏でありました。
続きましては、後半のエネスクについて。こちらでは、ベルチャSQのメンバーが上の声部を担当していました。
その演奏はと言いますと、作品の性格に依るところも大きいのでしょうが、かなり情念的なものとなっていました。扇情的でもあった。それは、ベルチャSQという団体の体質が反映された結果でもあったのでしょう。体当たり的な演奏ぶりで、音をガンガンぶつけてくる、といった感じ。この辺りは、メンデルスゾーンの最終楽章の、Gの4小節目での演奏ぶりを彷彿とさせるものだったと言えそう。
しかも、音楽は粗くならない。艷やかにして、豊潤な音楽が響き渡ることとなっていた。そして、音楽が随所でうねりまくっていました。
この作品は、数日前にNMLで聴いたのが初めてで、曲の構造といったものが把握できていないのですが、実演で接すると、かなりプリマドンナ型の作品だなと思えたものでした。第1ヴァイオリンの比重がかなり大きいのであります。更に言えば、第1ヴィオラにも重要な役割が与えられていることが多かった。そのために、シンフォニア・コンチェルタンテ的な色合いが感じられる音楽となってもいたのですが、その点については、ベルチャSQの2人が見事に応えてくれていたと言いたい。
第1ヴァイオリンは、先ほど来書いてきたように、扇情的であり、かつ、艶やかな音楽を奏で上げてくれていました。それに対して、第1ヴィオラは、煽情的になったり、大言壮語したり、といったことはなく、まろやかで、暖かみがあって、柔らかみを帯びていて、そのうえで、十分に艶やかなものとなっていた。鋭利な感じは全くなく、ふっくらとした音を響かせてくれていた。それでいて、音が埋没するようなことはなく、よく通る音がしていた。このヴィオラ奏者の音楽への志向に、感心させられました。そして、音楽性の豊かさや、センスの良さが感じ取れもした。
作品としては、エモーショナルであり、かつ、重厚なもの。弦楽器を8本使っている利点を生かそうといった意図の感じられるものだったと言えましょう。その一方で、各声部を有機的に絡ませる点においては、メンデルスゾーンに一歩も二歩も譲る、といったところでしょうか。作品自体の魅力ではメンデルスゾーンに及ばないと言いたいのですが、主としてベルチャSQの魅力を存分に感じ取ることのできた演奏となっていました。
アンコールでは、フォーレの≪レクイエム≫の終曲を弦楽八重奏に編曲したものが演奏されました。
清澄な演奏ぶりであり、心の平安をもたらしてくれるような演奏になっていました。編曲物ではありましたが、原曲の音楽世界をシッカリと伝えてくれる演奏だったと言いたい。そこには、この2つの四重奏団の音楽への誠実さが現れていたようにも思えたものでした。