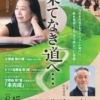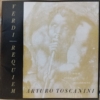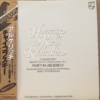下野竜也さん&兵庫芸術文化センター管による定期演奏会の第3日目(スメタナの≪わが祖国≫)を聴いて

今日は、下野竜也さん&兵庫芸術文化センター管(通称:PACオケ)による演奏会を聴いてきました。
演目は、スメタナの≪わが祖国≫の1曲プロ。第3曲の「シャールカ」が終わると20分間の休憩が採られる、という形での公演でありました。
各オケの演奏会に引っ張りだこだと言えそうな下野さんですが、私が実演に接するのは2年前の6月に聴いたPACオケとの演奏会以来。これには、ちょっと意外でありました。
そのときはオール・ショスタコーヴィチ・プロで、演奏されたのはピアノ協奏曲第2番と≪レニングラード≫。ダイナミックでありながらも、ゆとりのある音楽を奏で上げていて、風格のようなものが感じられた、聴き応え十分な演奏会でありました。
本日はどのような演奏を展開してくれるのだろうかと、期待に胸を膨らませながら会場に向かったものでした。

それでは、本日の演奏会をどのように聴いたのかについて書いてゆくことに致しましょう。
結論から申せば、期待を遥かに上回る、素晴らしい演奏内容でありました。2年前のショスタコーヴィチが、ダイナミックでありながら、ゆとりのある音楽づくりであったと書きましたが、その路線を延長させながら、更にシッカリとした土台の上に築き上げるような演奏ぶりだったと言いたい。
音楽の進行が、頗る逞しかった。音楽がしなやかに、かつ、豊かに息づいていた。しかも、こけおどしな表情が全くない。作品が望んでいる姿を描き上げようとした結果が、このような演奏になった、と言いたくなる演奏でありました。そのうえで、「雄渾」という表現がピッタリな演奏が繰り広げられていった。
と言いながらも、多少の不満はありました。例えば、第4曲の「ボヘミアの森と草原から」での、対位法的な手法が採り入れられている箇所などは、モゴモゴとした演奏になっていた。もっと、音の動きが克明で欲しかった。同じく「ボヘミアの森と草原から」での牧歌的な旋律が奏で上げられる場面では、音楽づくりがひ弱なものになってしまっていて、骨格の脆弱な演奏ぶりとなっていたように思えた。
かように、多少の不満を抱いた箇所もありました。しかしながら、それらは些細なこと。そのような不満を掻き消してしまうほどに、説得力の大きな演奏でありました。包容力の大きな演奏だったとも言いたい。そう、下野さんの、この作品への愛情、ひいては、音楽への愛情が滲み出ている演奏が展開されていた、というふうに思えてならなかった。
先ほども書きましたように、終始、ドラマティックで逞しい演奏が展開されていました。しかしながら、単に力だけで押し切るような演奏にはなっていませんでした。例えば、「モルダウ」の終わり間近な箇所で、トランペットが「高い城」での旋律を高らかに奏で上げていきますが、そこなどは、六分から八分くらいの力加減で、ゆとりを持って吹かせていました。そのために、決して、つんざくような音楽にはなっていなかった。むしろ、慈しむように演奏されていた。それでも、十分に輝かしかった。同じように言える場面が、全6曲の至る所で見受けられました。そのような、下野さんの判断の、なんと適切なこと。私には、そのように思えてなりませんでした。もっと言えば、下野さんの音楽センスの高さを感じたものでした。
効果を狙っているような素振りは微塵も感じられず、ひたすらに誠実に演奏をしてゆこうという意志を貫いていて、その結果として、効果の絶大な演奏が実現されていた。そんなふうにも言いたい。
しかも、音楽の動きや、運動性の発露や、といったものが、作品の内側から滲み出ているかのように、頗る自然だった。本日の演奏で、最も感嘆したのは、まさにここの部分でありました。であるが故に、切れば血が噴き出すかのような、バイタリティに溢れた演奏を繰り広げることができていたのだ、と。そして、生き生きと、かつ、しなやかに息づいている音楽を奏で上げることが可能となった。音楽が、至る所で唸りを上げることにもなっていた。もっと言えば、作品が、意志を持って躍動していた、とも思えてきた。
これらの点については、おそらく、本日の≪わが祖国≫での演奏態度がどうだった、といったことを越えて、下野さんの演奏家としての「土台」を成すものとして、体に染み付いていることだと言えるように思えます。下野さんは既に、そのような「すべ」を完全に手の内に収めている。いやはや、素晴らしい指揮者になったものだと言いたくなります。
そんなこんなのうえで、恍惚感の頗る高い音楽が奏で上げられていった。聴いている私もそうでありましたが、オケのメンバーもまた、恍惚としながら演奏していたに違いありません。下野さんは、そのような「すべ」もまた、手の内に収められているのであります。
下野さんは、ドヴォルザークを得意とされていて、その延長線上で、同じチェコの作曲家であるスメタナも素晴らしいだろうとは想像していましたが、想像の遥か上をいっていた。
今後、我が国のオケが、≪わが祖国≫を演奏しようと企画したならば、下野さんを指揮者に招いたら間違いない。そんな太鼓判を押したくなるような、作品との一体感の頗る強い演奏でありました。
かように、大満足の演奏会でありました。大興奮の演奏会にもなりました。次回以降の下野さんの演奏会が、いよいよ楽しみになります。
ちなみに、PACオケでは、10月の定期演奏会に登場されて、ブルネロを独奏者に迎えてのドヴォルザークのチェロ協奏曲や、伊福部昭の≪タプカーラ≫などを演奏することになっています。今から、楽しみでなりません。