ビーチャム&ロイヤル・フィルによるビゼーの≪アルルの女≫組曲を聴いて
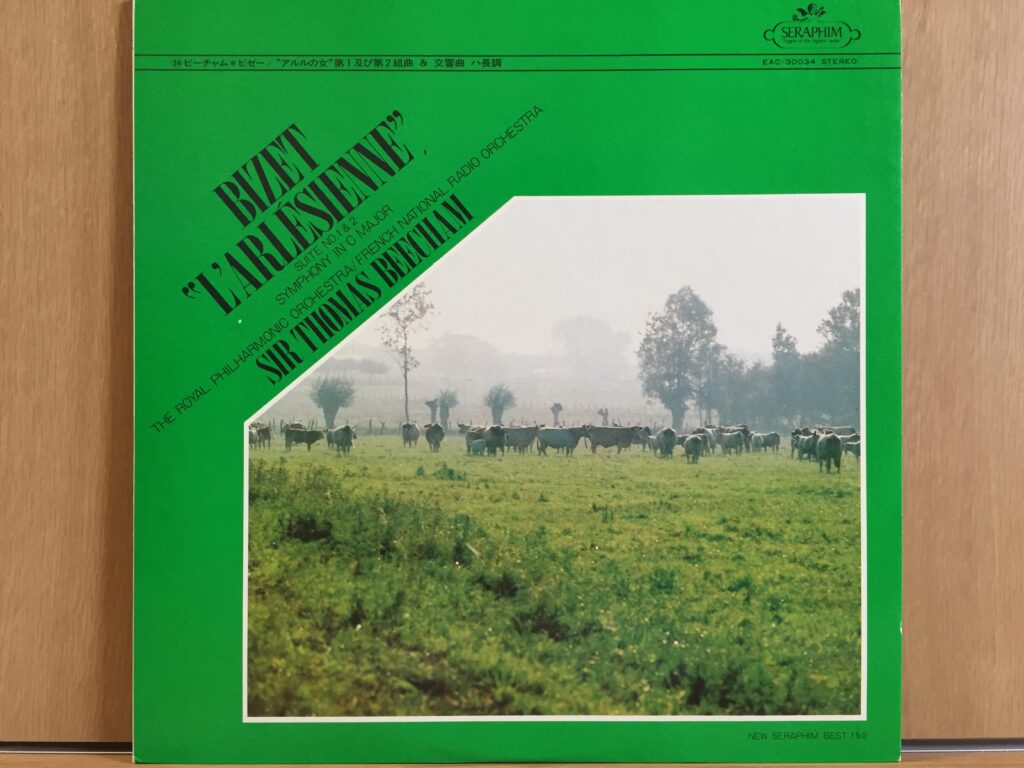
ビーチャム&ロイヤル・フィルによるビゼーの≪アルルの女≫第1,2組曲(1956年録音)を聴いてみました。
ビーチャムと言えば、好々爺然としていて、親し気で柔和な笑みを浮かべながら、円満で、おおらかな演奏ぶりを示す指揮者だというイメージが強いように思えます。そして、そこに暖かい雰囲気が織り込まれてゆく。
ところが、ここで繰り広げられている演奏は、そのようなビーチャム像とは異なったものが見出せます。克明な筆致によって、明快で、逞しい音楽が奏で上げられている。ある種、勇壮な演奏ぶりであると言っても良さそう。更には、適度な劇性が与えられている。気宇の大きさが備わってもいる。
ビーチャムは、このような演奏ぶりを見せてくれることも多いと捉えています。例えば、プッチーニの≪ラ・ボエーム≫全曲あたりが、その代表例と言えましょう。また、グリーグの≪ペール・ギュント≫の抜粋版でも、同様の演奏ぶりが示されている。ここまでに挙げた例は全て劇音楽である訳ですが、絶対音楽においても、似たようなスタイルの演奏に接することが、結構多い。
そのような演奏ぶりを踏まえたうえで、ビーチャムらしい暖かさを湛えた演奏となっています。親し気でもある。そして、凛とした音楽となっている。優美さが感じられもする。
そして、ここでの演奏を通じて、≪アルルの女≫が、キリっとしていて、かつ、洒脱な佇まいを見せてくれている。劇音楽としての、生命力の豊かさが伝わってくる。そういったことがまた、なんとも魅力的。
ビーチャムの演奏の、幅の広さが実感できる記録。このようなビーチャムも、とても素敵であります。






