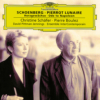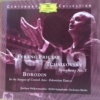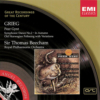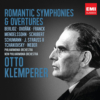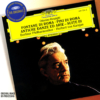鈴木秀美さん&神戸市室内管によるベートーヴェン・ダブルビルの第2日目(第九)を聴いて

昨日に引き続いて、鈴木秀美さん&神戸市室内管(略称:KCCO)による演奏会を聴いてきました。演目は、ベートーヴェンの第九。
独唱陣は、下記の通りであります。
ソプラノ:中江早希さん
アルト:布施奈緒子さん
テノール:櫻田亮さん
バス:氷見健一郎さん
合唱は、神戸市混声合唱団でありました。
ベートーヴェン・ダブルビル(「二本立て興行」の意)の第2日目。指揮者もオーケストラ、更には合唱と独唱者も、昨日と全て同じ陣容で演奏される第九であります。
昨日の≪ミサ・ソレムニス≫は、誠実かつ素朴でありつつ、曲想に応じて雄渾な性格も織り込まれていた演奏が繰り広げられていました。そのうえで、暖かみがあって、清々しくもある≪ミサ・ソレムニス≫となっていました。
本日も、その延長線上で第九が鳴り響くのではないだろうか。そんなふうに予想しながらの鑑賞でありました。
それでは、本日の演奏会をどのように聴いたのかについて書いてゆくことに致します。

予想に近い演奏が繰り広げられました。全体的に、シェイプアップされた第九になっていた。そして、総じて、昨日の「キリエ」で受けた印象に近いものだったと言いたい。
ちなみに、弦楽器のプルトの数は4-4-3-2-1.5。私の席(2日とも同じ席での鑑賞)からはヴァイオリン群の並びが見えにくかったのですが、昨日も同じ編成だったと思われます。シェイプアップされた演奏だったという印象は、こうした小規模なオケによる演奏だったことに依るところが大きかったのは、間違いないでしょう。
なお、古楽器系の演奏家だと言える鈴木秀美さんですので、第2楽章では全てのリピートが実行されていました。それは、ダ・カーポした後のスケルツォ部でも、最初のリピート(150小節目)を実行したほど。但し、さすがにと言いましょうか、ダ・カーポ後の後半(151小節目以降)は、1番カッコに入らずに2番カッコに入っていました。
また、古楽器系による演奏ということで興味を惹かれたのは、第3楽章の真ん中辺りで現れる3番ホルンによるソロ(83小節目から)。鈴木さん&KCCOは、常にナチュラルホルンを使用しています。そこで、ナチュラルホルンではゲシュトップ奏法を採り入れないと出せない音が現れています。そうであるが故に、15小節間ほどにわたるソロのクライマックスと呼べる16分音符によるパッセージ(96小節目)では、音符の半分ほどはゲシュトップで吹くことになっていました。その結果、半分ほどの音が引っ込んでしまっていた。なんとも不自然なのですが、これはナチュラルホルンという楽器の機構上、仕方ないことであります。そのことが解っていますので、逆に何とも言えない面白みが感じられた次第。この16分音符によるパッセージは、失敗も多いため、スリルを感じながら聴いていた(そこには、「見守る」といった心情も湧いています)のですが、フレーズの最初の方をややゆっくりと吹いて、後半でその分を取り返すべくちょっと煽って吹く、といった対処法を採りながら、吹き損じすることなく吹いていて、見事でありました。私も、胸を撫で下ろした、といった感じに。
さて、ここからは本筋の話しと言いましょうか、本日の音楽づくりについて。
時に速めのテンポが採られることもありつつも、概して、速からず遅からず、といったところだったでしょうか。例えば、第3楽章の冒頭の2小節間は、通常の倍近い速さで演奏され、ひょっとすると、この楽章はこのまま超快速でスイスイと奏で上げてゆくのだろうか、など思ったりもしたのですが、3小節目からは、ほぼ通常のテンポで演奏されていきました。また、最終楽章でのトルコマーチの箇所も、オケだけを聴いていると通常のテンポだなと感じられつつ、テノール独唱が入ると、そこでテンポを上げた訳ではないのにも関わらず、速いテンポだな、と感じられた次第。このことから思い当たったのは、オケの、贅肉を削ぎ落としたような響きによって、鈴木さんが採っている速めのテンポを、それほど速いと感じさせなかったのかもしれないな、ということでした。
今述べたことと関連することになりましょうが、鳴り響いている音楽は、重苦しくなったり、ダブついてしまったり、といったことの全くないものになっていました。とても清新な第九になっていた。
それでいて、キビキビとした音楽づくりになっているな、といった印象もあまり受けなかった。或いは、軽妙な演奏ぶりになっているな、とも思えなかった。第九の持っている質量を、爽快感を漂わせながらもシッカリと表出していた演奏だったと言いたい。そのうえで、厚ぼったくなることなく、清々しい第九が鳴り響いていた。
更には、熱くなるべき箇所では、シッカリと熱くなっていた。逞しさを出して欲しいところでは、必要十分に逞しく奏で上げてくれていた。この辺りは、昨日の≪ミサ・ソレムニス≫での「グローリア」や「クレド」での演奏ぶりと同様であります。
それらに加えて、凝縮度の高い音楽が鳴り響くことがしばしば。キリッとした表情を随所に見せてくれていました。或いは、決然とした表情や、意志の力の強さといったようなものも随所で湛えていた。それらが、作品を深く抉ってゆくことに繋がっていたと言いたい。また、要所要所を際立たせてくれてもいた。
そんなこんなの美点を認めつつも、総じて、軽量級の第九だったという思いが拭い去れません。逞しさが備わっていながらも、壮麗な音楽になっていた訳ではなかった。そして、踏み込みに不足していたと感じられることが多かった。そういったことへの不満は、昨日の≪ミサ・ソレムニス≫以上だった、というのが正直なところであります。
なお、独唱陣についての印象は、昨日と大きく変わることはありません。
そのような中で、バスの氷見さんによる出だしのソロは、凛としていて、かつ、朗々としていて、押し出しもシッカリしていて、実に立派でありました。そして、その後はあまり出しゃばらない。ツボを押さえつつ、慎ましさを備えている歌唱だったと言えるのではないでしょうか。
また、ソプラノの中江さんは、昨日同様に、意識的にヴィブラートを抑えていたようです。そのことがハッキリと窺えたのが、832小節目からのPoco adagioの箇所。この、4人の独唱陣によるカデンツァ風な箇所で、とりわけ中江さんは、ヴィブラートを殆ど掛けずに、実に清澄な歌を聞かせてくれていました。そのことによっては、清潔感漂う美しさが生まれ、聴き惚れたものでした。
更には、テノールの櫻田さんは、キリっとした佇まいをしていて、かつ、リリカルな美しさを湛えた歌唱を繰り広げていた。アルトの布施さんは、必要十分に深々としていた。
全ての独唱者が、薫り高い歌を繰り広げてくれていたと言いたい。
更には、合唱陣もまた、過度に厚ぼったくなることなく、それでいて、非力なところも全くなく、かつ、清潔感を漂わせながら、立派な歌唱を繰り広げてくれていました。とりわけ印象的だったのは、594小節目からのAndante maestosoの箇所。この、3本のトロンボーン(そして、チェロとコントラバスも音を重ねている)がサポートしながらのコラールを、キリっとした表情を湛えながら、威厳タップリに歌い上げていました。しかも、清潔感を損なうことがなかった。本日の合唱で、最も魅了された箇所となっていました。
縷々書いてきましたが、総じて、誠実さに溢れた演奏ぶりであり、興味深い点の多々あった演奏ではありつつも、今一つズシリとした手応えを持つに至らなかった第九だった。そんな思いを抱きながら、会場を後にしたものでした。