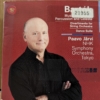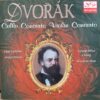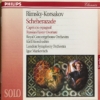鈴木秀美さん&神戸市室内管によるベートーヴェン・ダブルビルの初日(ミサ・ソレムニス)を聴いて

今日は、鈴木秀美さん&神戸市室内管による演奏会を聴いてきました。演目は、ベートーヴェンの≪ミサ・ソレムニス≫。
独唱陣は、下記の通りであります。
ソプラノ:中江早希さん
アルト:布施奈緒子さん
テノール:櫻田亮さん
バス:氷見健一郎さん
合唱は、神戸市混声合唱団でありました。
ベートーヴェン・ダブルビル(「二本立て興行」の意)と銘打って、今日明日の2日間で≪ミサ・ソレムニス≫と第九を演奏する、鈴木秀美さん&神戸市室内管のコンビ。更には、合唱と独唱者も、両日とも同じ陣容。なんとも意欲的な企画であります。
鈴木さんならではの真摯にしてアグレッシブな態度が貫かれた演奏で、ベートーヴェン晩年の大傑作を聴くことができるのではないだろうか。そんな期待を胸に秘めて、会場に向かったものでした。
なお、休憩なしで一気に全曲を演奏するのであろうと予想していたのですが、第2曲目の「グローリア」の後に休憩を挟んでの公演となりました。
それでは、本日の演奏会をどのように聴いたのかについて書いてゆくことに致します。

ホールの前のイチョウは見事に色づいていました。
このイチョウ、見応えがあります!!

また、ホール裏の公演の楓も、赤く染まっていました。
弦楽器のプルトの数は4.5-4-3-2-1.5だったでしょうか。合唱団員は女声も男声も、それぞれ20名弱で、総勢35名ほど。そのような小規模な演奏者たちによる≪ミサ・ソレムニス≫だったということもあり、第1曲目の「キリエ」は、荘厳な雰囲気といったものが立ち昇らない演奏となっていました。何と言いましょうか、手作り感のある≪ミサ・ソレムニス≫が始まったな、といった印象を受けもした。市井人ベートーヴェンによる音楽、といった感じでもあった。
更には、音楽づくりに暖かみや、親しみといったものが感じられもした。この辺りは、鈴木秀美さんならではだと言えましょう。そして、頗る誠実でもあった。
演奏者が小規模だったが故に、音楽が引き締まってもいた。
とは言うものの、踏み込みの不足のようなものを感じずにはおれませんでした。この作品に備わっていて欲しい、壮大な音楽世界が広がってゆく、といったものも乏しかった。
しかしながら、第2曲目の「グローリア」に入ると、演奏の様相は一変しました。音楽が一気に生気を帯び始め、輝かしくなったのであります。頗る勢いが良かった。それはまさに、グローリアと称されるに相応しいものだった。
とは言うものの、音楽が粗くなるようなことはない。それよりももっと、凝縮度の高い音楽になっていた。
これから先も、ナンバーによって、かなり異なった演奏ぶりが為されてゆくのではないだろうか。そのような思いを抱きながら、休憩に入ったのでした。
第3曲目の「クレド」以降になりますが、前半が終わったところで予想しましたように、ナンバーによって印象の違う演奏が展開されていきました。それは、素朴さと雄渾さが交錯する演奏だったと言えば良いでしょうか。「グローリア」までを聴いていた際には「手作り感」といった言葉が頭をもたげたのですが、「素朴さ」と言ったほうが相応しいように思えてきた。
その素朴さが際立ったのは、終曲の「アニュス・デイ」も終わろうとしている箇所、2分の2拍子でありつつも、1小節単位で捉えると大きな3拍子のようにして進んでゆくところ(266小節目、ここからPrestoになる)であります。ここは、様々な声部や旋律がぶつかり合い、相克し合いながら突き進んで欲しい。しかしながら、それらが激しくぶつかり合う、といった様相からは遠いものになっていたのです。「キリエ」で感じたように、踏み込み不足な音楽になっていた。というよりも、小規模な編成が採られているが故の響きの薄さが露呈されてしまった、と言ったほうが良いでしょうか。
なお、「アニュス・デイ」は、この箇所に限らず、総じて穏当な音楽づくりに過ぎたような印象を受けました。本日の≪ミサ・ソレムニス≫の演奏は、音楽が勢いよく邁進してゆくことのないナンバーは概して、生き生きとした表情に乏しいものになっていたように思えたものでした。
その一方で、「クレド」では、「グローリア」と同様に、輝かしくて逞しい音楽が奏で上げられていました。それこそ、とても雄渾な音楽になっていた。音楽が奔流となって突き進んでいた。
しかも、それが単に力づくで押し進めてゆこう、といったものになっていなかった。音楽を推進させてゆく力が、とても適切で、場違いなものになっていなかったとは言いたい。この辺りは、鈴木さんの音楽センスの良さや、見識の高さや、ひいては、人間性や、といったものに依るのでしょう。
また、「クレド」ももう終わろうとしているところで、オケのトゥッティによる強奏ともに“Amen, Amen”と重ねて歌われる箇所(463小節目)では、音をキッと切り詰めた形に凝縮させて響かせていたのが、とても印象的でありました。それは、とても決然とした音楽になっていた。更には、強い意志が滲み出ていたとも言えそう。なるほど、ここにはスタカートが付けられています。ベートーヴェンが記したスタカートが、効果的に生かされていたと言いたい。
第4曲目の「サンクトゥス」は、緩やかなテンポを基調としたナンバーではありますが、鈴木さんによる誠実な音楽づくりが生かされていて、抒情性豊かな演奏が繰り広げられていました。良い意味で穏やかな演奏だった。救いに満ちた音楽だったとも言えそう。但し、この後半の「ベネディクトゥス」でのコンマスソロは、オケと合唱に埋没してしまっていたのが残念でした。音色も、演奏ぶりも、清冽なものだっただけに、もっと周りの音を乗り越えたところで音楽を響かせる、といったものであって欲しかった。なお、この「ベネディクトゥス」の箇所でも、鈴木さんによる音楽づくりは、淀みがなくて、優しさに溢れたものになっていました。コンマスソロへの優しい眼差し、といったようなものが感じられもした。
本日の≪ミサ・ソレムニス≫は、総じて、厳しさの無いものだったと言えましょうか。急速な箇所ではバイタリティ溢れる音楽が鳴り響いていましたが、壮麗さが滲み出てくるようなものになっていた訳ではなかった。その意味では、総じて、素朴さの優った演奏だったと言えましょうか。それは、鈴木さんの音楽性と、本日の編成の規模に依るものだったのだと言いたい。
なお、独唱陣では、テノールの櫻田さんに最も惹かれました。とても清冽であり、かつ、凛々しい歌いぶりでありました。そのような中、「アニュス・デイ」での“miserere”と歌う箇所(182小節目から、ここにはレチタティーヴォと記されている)に限って、とてもドラマティックに歌っていたのが印象的でした。
バスの氷見さんは、総じて抑制の効いた歌いぶりだったと言えましょうか。突出するようなことが全くなく、下からシッカリと支えていた、といった感じ。そのような中で、「アニュス・デイ」の冒頭でのソロは、バスにとって一番の聴かせどころと言え、ここでもまた、押し付けがましさが全く感じられないながらも、朗々としていて、ノーブルな歌を披露してくれていました。
ソプラノの中江さんもまた、清潔感のある歌いぶり。意識的にヴィヴラートを抑えて歌っていたと思われる箇所も多く、そのことが、清潔感を増してくれていました。しかも、絶叫するようなことは皆無でなりながら、声がよく通っていて、存在感の大きな歌唱となっていました。
アルトの布施さんは、必要十分に深々としていて、かつ、響きがくぐもるようなことはなく、まっすぐな歌いぶりとなっていました。
独唱陣は4人とも、伸びやかさのある歌唱だったと言えましょう。クセのない、誠実な歌いぶりだったとも言いたい。それがまた、鈴木さんの音楽づくりにピッタリでありました。
合唱団は、人数は決して多くないながらも、「グローリア」や「クレド」での鈴木さんによって雄渾にして輝かしい音楽づくりが施された箇所でも、その輝かしさを十分に支えてゆく歌唱を展開していって、見事でありました。しかも、勇壮な性格を前面に押し出す必要のない箇所では、清潔感を備えていて、キリっとした合唱を繰り広げてくれていた。その辺りも含めて、立派な合唱だったと言いたい。
指揮者もオケも、更には、独唱者も合唱も、基軸を一にした演奏だった。そんなふうに言えるのではないでしょうか。
その結果として、膨満感を覚えることがない≪ミサ・ソレムニス≫が展開されていった。そして、暖かみがあり、それでいて、清々しくもある≪ミサ・ソレムニス≫が展開されていった。そんな、ユニークな魅力を湛えた≪ミサ・ソレムニス≫でありました。