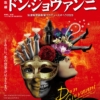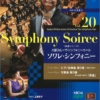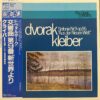佐渡裕さん&兵庫芸術文化センター管によるブリテンの≪戦争レクイエム≫の第2日目を聴いて

今日は、佐渡裕さん&兵庫芸術文化センター管(通称:PACオケ)による演奏会の第2日目を聴いてきました。
演目はブリテンの≪戦争レクイエム≫。独唱者は、並河寿美さん(S)、小原拝楼さん(T)、キュウ・ウォン・ハン(Br)でありました。また、別動隊の室内オーケストラを指揮したのは齋藤友香理さん。
今年は終戦80年の節目の年。佐渡さんは、反戦と平和への思いを込めて採り上げることにした演目だという点を、事前にかなり強調されていました。しかも、今年は、兵庫県立芸術文化センターの開館20周年。
(もっと言えば、今日は「長崎の日」でもあった。)
そのようなメモリアルが2つ重なっている年に、この作品を演奏するということの意義の大きさたるや、計り知れないものがありましょう。今年度のPACオケによる定期演奏会のハイライトと呼べそうな演奏会だったとも思えます。
滅多に採り上げられることのない≪戦争レクイエム≫の実演に接することができるという、貴重な機会。先月にはノット&東京交響楽団がステージに乗せているようですが、終戦80年の節目の年であるからこそ、このようにプロジェクトが重複したのでありましょう。
本日の佐渡さん、きっと集中力の高い演奏を繰り広げてくれることであろうと、大いに期待していました。とりわけ、最後の部分での静謐にして敬虔で崇高な雰囲気が立ち込めていき、魂が浄化されるかのような音楽を、いかに感動的に奏で上げてくれるのであろうかというところに、大注目していました。また、独唱陣では、ここのところ実演に接する機会が多く、かつ、感心させられることの多い並河さんが、とても楽しみであった。
それでは、本日の演奏をどのように聴いたのかについて、書いてゆくことに致しましょう。

聴いた後に湧いてきたもの、それは、滅多に実演で接することのできない作品に触れることができたのだな、という感慨でありました。この、メッセージ性の極めて高い大作を。そのような機会に恵まれたことを有り難く思った、というのが率直なところでありました。やはり、感じ入るものがあった。
とは言うものの、その演奏内容については、ちょっと微妙だったかな、といったところ。多くの演奏家が関わっていた、本日の演奏会であります。演奏全体を通じて、感心させられる点は数多くありました。その一方で、もっと深く掘り下げることも可能だったのでは、と感じられる箇所も散見されました。そのために、このようなモニュメンタルな大作が演奏されたにも拘らず、終演後にブラヴォーが全く掛からなかったということも、頷けました。
最も感銘を受けたのは、終曲の「リベラ・メ」でありました。ここまでの佐渡さんによる演奏ぶりは、ただただ音楽をやり過ごすといった箇所が多く、無為に流れてゆくことが多かった。そのような演奏ぶり(或いは、演奏態度と言っても良いかもしれません)は、佐渡さんの演奏でしばしば感じられることなのですが。
(全てが全て、そうだったとは言いません。)
何と言いましょうか、この作品が抱えている「慟哭」といったものが表に現れずに、音楽がサラサラと流れていくことが多かった、とも感じられたのでした。音楽が弛緩していた場面が多かったとも言いたい。
ところが、「リベラ・メ」に入ると、音楽の凝縮度が一気に上がった。音楽が渦巻いてゆくようにもなった。音楽が俄然、生き生きとしてきたのであります。その印象は、先月接した≪さまよえるオランダ人≫での、序曲とオペラ本編に入ってからのギアの入れ方の違いに通じるものであった。
「リベラ・メ」は、この作品の頂点であり、メッセージ性が最も高いと思われます。それ故に、そこに至って初めて、佐渡さんは思いを爆発させた、といったところだったのでしょうか。
そのうえで、最後の清浄な音楽世界が広がる場面では、崇高な音楽が響き渡っていった。それは、この箇所が元来備えている性格を、過不足なく描き上げてくれている演奏になっていたとも言いたい。また、最後の音が伸びている最中に、佐渡さんは両手で指揮棒を握りしめ、祈りを捧げるようでもありました。
(私が気付いた範囲では、両手で指揮棒を握りしめて祈りを捧げる姿を見せたのは、この最後の最後だけだったようでした。)
このような形で演奏を閉じたが故に、≪戦争レクイエム≫の実演に接することができた満足度といったようなものが、グッと上がったのだと言えましょう。しかも、「リベラ・メ」の後半部分は、演奏前から大注目していた箇所でもありましたので。
さて、「リベラ・メ」だけではなく、他の箇所でも、佐渡さんの音楽づくりに感心させられた箇所はありました。それは、以下のような箇所において。
冒頭の「レクイエム」の出だしなどは、音楽の抑揚に合わせて、佐渡さんは上半身を前後に揺らして、この音楽が宿している「音楽の鼓動」といったようなものが、豊かに表現されていました。≪さまよえるオランダ人≫での音楽が波立つ場面で、佐渡さんの身体が波打つようなことが少なかったこととは、大きな違いを感じた。
しかしながら、それが長続きしないのが、私には不思議なのであります。音楽を抑制させながら、理性的な音楽を目指す、ということが、佐渡さんのポリシーなのでしょうか。なるほど、それも一つの行き方でありましょう。しかしながら、佐渡さんによる演奏は、音楽に命が吹き込まれない形で抑制させてゆく、といったものであるように思えてならないのであります。
話しを続けましょう。
第2曲目の「ディエス・イレ」の真ん中辺り、音楽が5拍子で進んでゆく場面や、更にその後に、7拍子で流れてゆく箇所での佐渡さんの音楽づくりには、躍動感が備わっていて、逞しさを宿していました。その結果として、音楽にシッカリと命が吹き込まれていたようにも感じられた。
佐渡さん、「やればできるのに」という思いをしばしば抱いてしまいます。それだけに、佐渡さんによる演奏に接していますと、なんだか勿体ない気がしてならないのであります。
かように、佐渡さんによる指揮には、疑問に思う点も多々あったのですが、室内オーケストラの指揮を担当していた齋藤友香理さんが見事でありました。とても鋭敏な指揮ぶりで、かつ、音楽づくりがしなやか。アゴーギクの変化も鮮やかで、かつ、自然。そんなこんなによって、目鼻立ちのクッキリとした音楽が奏で上げられていた。表情が豊かであり、的確でもあった。それだけに、佐渡さんの音楽づくりが余計に「のんべんだらり」としたものに思えてきたものでした。
独唱陣では、やはりと言いましょうか、ソプラノの並河さんが見事でした。ドラマティックでありつつも、優しさが感じられもした。総じて、貫禄タップリな歌いぶりでありました。それでいて、誇張が感じられなかったところにも感心させられました。
また、テノール小原さんとバリトンキュウ・ウォン・ハンの2人は、性格的な歌唱だったと言いましょうか。特に、「リベラ・メ」での心情の吐露にはグッと惹き込まれ、説得力の高い歌唱だったと言いたい。
感心させられた点と、不満に感じた点とが織り交ぜになっていた≪戦争レクイエム≫ではありましたが、総じて、大きな破綻のない演奏だったと言いたい。作品の「実体」のようなものをシッカリと掴むことのできた演奏でもあった。
欲求不満を抱えつつも、貴重な機会を得ることができたという思いを抱きながら、会場を後にしたものでした。