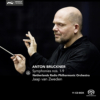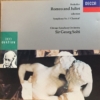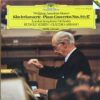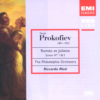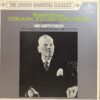デュメイ&関西フィルによる演奏会(モーツァルト、ベートーヴェン、ブラームスを並べたプログラム)を聴いて

今日は、デュメイ&関西フィルによる演奏会を聴いてきました。演目は、下記の3曲。
●モーツァルト 交響曲第29番
●ベートーヴェン ピアノ協奏曲第4番(独奏:フルネル)
~休憩~
●ブラームス ≪ハイドンの主題による変奏曲≫
指揮を務めるデュメイは、2011年から昨年までの13年間にわたって関西フィルの音楽監督の任にあり、今季からは名誉指揮者に就いています。
モーツァルト、ベートーヴェン、ブラームスによる、オーソドックスな作品が並んでいる、本日の演奏会。それでいて、ブラームスの≪ハイドン変奏曲≫をトリに据えているというのは、異色なプログラミングだと言えましょう。しかも、休憩後は≪ハイドン変奏曲≫のみという、時間的に見て、かなりアンバランスな構成になっている。
デュメイは、表現意欲が旺盛で、かつ、情熱的な音楽づくりを施す演奏家だと看做していますが、本日は、優美な性格の強い作品で彩られているように思えます。そのような作品たちを、デュメイはどのように演奏してゆくのだろうか。とても興味深いところでありました。
また、ピアノ独奏を務めるフルネルは、2021年のエリザベート王妃国際コンクールの優勝者だということ。そして、ヴァイオリニストしてのデュメイとは、室内楽での共演を重ねているようです。
今年32歳の、若手ピアニスト。はたして、どのようなピアノ演奏を繰り広げてくるのかと、こちらも楽しみでありました。
それでは、本日の演奏会をどのように聴いたのかについて書いてゆくことに致します。

まずは前半からになりますが、やはりと言いましょうか、とても長い前半になりました。ソリストアンコールも含めると、1時間15分ほど掛かった。
さて、そこでの演奏はと言いますと、前プロのモーツァルトは、デュメイならではの表現意欲の強い演奏になっていました。ある種、手練手管を弄したモーツァルトだったと言いたい。ちょうど1週間前に聴いたプレトニョフによる協奏曲と相通ずるようでもあった。
まずもって、最初の音が鳴り響いた瞬間、関西フィルの艶やかな響きに魅了されたものでした。この艶やかさは、関西フィルの体質であり、美質だと思っています。響きが明るくもある。そのような特質を生かすべく、デュメイは主にレガートを効かせながら、滑らかな音楽に仕上げてゆこうと志向していたようです。
そこまでは称賛したところなのですが、いかんせん、デュメイは表情をタップリと付け過ぎていたように思えてならなかった。旋律に起伏を付けていったり、小節の頭にアクセントを施したりと、とても饒舌なモーツァルト演奏だったとも言いたい。例えば、第2楽章の第2主題に入る前のアウフタクトでは、グッとテンポを落として、ためらいがちな表情を施しながら勿体ぶってみせたりする。
総じて、感情移入の強いモーツァルトだったとも言えましょう。しかしながら、それが私には煩わしかった。もっと、素直に演奏しても良いのに、と思えてならなかった。
更には、第3,4楽章では、フレーズによっては突然に元気になったりして、それも恣意的で、不自然だった。
私のモーツァルト観からは大きく隔たった演奏でありました。しかも、モーツァルトの交響曲の中でも屈指の、可憐で、かつ、無垢な美しさを備えている第29番での演奏だったことが、そのようなわだかまりをより大きくしてしまったものでした。
続くベートーヴェンでのデュメイの演奏スタイルは、モーツァルトの時とあまり変わりませんでした。但し、こちらは、モーツァルトに比べると、音楽が大柄になり、かつ、ロマンティックな性格を帯びてきますので、表情豊かなデュメイの音楽づくりを作品がシッカリと受け止めてくれていたように思えたものでした。そのために、モーツァルトほどには違和感なく聴くことができた。
そのようなデュメイの音楽づくりに対して、フルネルは屈託のない演奏を展開してくれていました。デュメイよりも、かなり率直な音楽づくりだったと言いたい。なおかつ、タッチが繊細で、音が柔らかい。響きが、とても美しくもあった。そのために、とてもリリカルなピアノ演奏が繰り広げられていったのでありました。
とは言うものの、ちょっとお行儀が良すぎるかな、といった印象を持ちながら聴き進んでいったものでした。
ところが、第1楽章のカデンツァに入ると、フルネルの演奏ぶりが一転しました。オケによる束縛から解放されたかのように、自在に、かつ、勇壮に弾いていったのであります。この、ベートーヴェンのピアノ協奏曲の中では女王のごとくエレガントな雰囲気を持っている第4番を、であります。振幅がとても大きくて、しかも、そこに偽りのない心情が吐露されてゆくような弾きぶりだったとも言いたい。
前述したように、フルネルはデュメイと室内楽を演奏する機会を持っているようですが、そこでは、フルネルはリードしてもらう立場を採ることが多いのかもしれません。そのような両者の関係が、本日のフルネルの演奏を、消極的なものにしてしまっていたのだろうか。そのように想像してしまいました。
いずれにしましても、カデンツァでの演奏に、フルネルの真実があった。そんなふうに言えるような演奏でありました。
ところで、フルネルとデュメイとの関係は、アンコールを演奏する段になっても見受けられました。と言いますのも、なかなかアンコールを演奏しようとしないフルネルに対して、「ほら、もうアンコールを演奏しなよ」とばかりに促していたのであります。
そのアンコールでは、バッハ作・ジロティ編曲による≪前奏曲≫ロ短調が弾かれました。
その演奏はと言いますと、アンニュイな雰囲気の漂う演奏ぶりでありましたが、こちらでも、カデンツァで聞かせてくれたような自らの殻を破ったような演奏にはなっておらずに、お行儀の良さが出ていたように思えたものでした。
その代わりに、なんとも精妙な音楽が鳴り響いていた。それは、フルネルの抒情性の豊かさと、音色の美しさ故なのでありましょう。

ここからは、メインの≪ハイドン変奏曲≫について。
こちらもまた、デュメイらしく表現意欲の旺盛な演奏でありました。但し、モーツァルトの29番ほどには鼻につくことはありませんでした。それはやはり、作品自体がロマンティックな性格を備えているからでありましょう。
更には、オケの音の艷やかさが、とても有効に働いていたようにも思えたものでした。モーツァルトでの演奏と同様に、そういった関西フィルの特質を生かすべく、レガートを効かせながら、滑らかな音楽に仕上げてゆこう、といった意図が感じられた。そういったことに加えて、≪ハイドン変奏曲≫では、小気味良い音楽づくりを曲想に応じて織り交ぜながら、演奏を繰り広げていた。これもまた、ブラームスというロマン派の作曲家による作品であるが故の多彩な対応だったのだと言えましょう。
個性的だったのが、第3変奏での、後半部分をリピートする際に現れるホルンの上昇パッセージを、スラーではなくスタカートで吹かせたこと。この辺りに、単に滑らかに仕上げるのではなく、小気味良さを付加しようという意図が滲み出ているように思えます。
とは言いましても、やはりデュメイの本領が発揮されるのは、レガートを効かせながら艶美に演奏してゆくところに現れていたと思えます。それは、彼のヴァイオリン演奏と共通したことだと言えそう。
なお、リピートをシッカリと励行していたのは、大いに支持したい。これはモーツァルトでも然りで、第1,2,4楽章の主題提示部をシッカリとリピートしていました。やはり、こういったリピートを励行してゆけば、音楽のフォルムに芯が通ってゆくように思えます。
ただ、≪ハイドン変奏曲≫での第2変奏の後半部分をリピートする際に、ついつい気が緩んでしまったように僅かにリタルダンドを掛けてしまい(リピートせずに終結させてしまいそうな雰囲気を漂わせたリタルダンド)、オケが戸惑ってしまってアンサンブルが乱れたのは、思いがけないアクシデントでありました。
また、終曲のパッサカリアに入る2つ前になる第7変奏では、3拍子の流れの中に2拍子の歩みが現れる場面が2ヶ所あるのですが、そこをデュメイは2拍子で振っていました。そのことによって、このようなカラクリを施したが故の妙味(それは、得も言われぬ揺らぎのようなもの、だと言えば良いでしょうか)が消えてしまい、拍節感の安定した音楽になっていたのが、ちょっと残念でありました。しかも、この変奏が終わる箇所では、2拍子で振っていたための辻褄合わせが上手いこといっていなくて、楽譜よりも多くの拍が含まれてしまったようになっていた(リピートした後の2回目に、目を瞑りながら3つ振り、と言いますか、3拍子を大きく1つに採りながら手元で手を動かしていたのですが、デュメイ&関西フィルが奏でていた演奏は、余りが生じていたのであります)のは、頂けません。デュメイ、ブラームスの交響曲第4番の最終楽章での同様な拍子配分になっている箇所でも、同じ対処方法を採るのでしょうか。デュメイの指揮者としての技量を不安視してしまった箇所になりました。
と、ここまでは主としてマイナス面を書いてきましたが、感心させられる点もありました。それは、デュメイのロマンティシズムを追求する姿勢が、ブラームスの音楽に合致することが少ながらずあったこと。更には、音楽を豊麗に鳴らすこともしばしばで、充実した音楽が掻き鳴らされていた点など。その一方で、リリカルな表情を湛えている箇所では、情緒タップリな音楽が奏で上げられていた点、など。
そんなこんなもあり、面白く聴けた箇所もありましたが、疑問に思える箇所も多く、概して、もどかしさを覚える≪ハイドン変奏曲≫でありました。