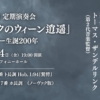尾高忠明さん&大阪フィルによる西宮公演(4/27開催)を聴いて

今日は、兵庫県立芸術文化センターで、尾高忠明さん&大阪フィルの西宮公演を聴いてきました。演目は、下記の2曲。
●シューベルト ≪未完成≫
●ブルックナー 交響曲第9番
シューベルトとブルックナーによる、未完成の2つの交響曲を組合わせたプログラム。よくある組合せだと言えましょうが、実に魅力的なプログラムであります。
(聴きには行けていませんが、ヴァントが亡くなる前年の2000年に、北ドイツ放送響と来日して催された演奏会も、同じプログラムでした。)
この両曲を、尾高さんと大阪フィルのコンビがどのように演奏するのだろうかと、期待に胸を膨らませながら会場に向かったものでした。

それでは、本日の演奏会をどのように聴いたのかについて、書いてゆくことに致します。ますは、前半のシューベルトから。
誠実で、オーソドックスなスタイルが貫かれた演奏だったと言えましょう。そこには、尾高さんらしさが詰まっていたように思えたものでした。
基本的には清々しさのようなものが感じられる演奏ぶりでしたが、決して軽量級な演奏だった訳ではありません。重すぎるようなことにならない範囲で、重量感を持った演奏が展開されていたのであります。
テンポはやや遅め。シッカリと歩調によって、音楽は進められてゆく。しかも、流れが淀むようなことはなく、自然な呼吸をしていた。時にタメを作るようなことがありつつも、頻繁に施す訳ではないために、煩わしくはない。その辺りのバランスも含めて、なかなかの秀演だったと言いたい。
そんなこんなによって、≪未完成≫の音楽世界に、ドップリと身を浸すことのできる演奏でありました。それはまさに、「正統的な演奏」と呼ぶに相応しいとも言えそう。
そのうえで、色々と創意工夫が施されていたように思えます。と言いますのも。
冒頭のチェロ・バスの旋律は、ほぼノンヴィブラートで奏でられていた。その表情は、淡々としていて、かつ、儚げでありました。猟奇的と言えば言い過ぎでしょうが、少々、恐ろしげでもあった。確かに、冒頭には、そのような性格が備わっているように思えます。それでいて、第1楽章のリピートを行って冒頭に戻った際には、1回目よりもヴィブラートを多めにして、音量も上げ、儚さや恐ろしさよりもロマンティシズムを強調するようになっていた。音楽の表情が、濃厚になってもいた。その変化に、リピートした意味を、考えさせられたものでした。一度、提示部を丸々演奏したことによって、心境に変化が生じてくる。音楽が温まってもくる。その変化を、意図的にハッキリと表したのではないだろうか。そんなふうに思えたものでした。
その一方で、リピートしてから演奏された第2主題は、かなり音量を抑えて、消え入りそうな音楽として奏でていた。リピートする前の1回目は、そのことに気付かなかったため、恐らく、音量を抑えるようなことをしていなかったのでしょう。ここにも、リピートによる表情の変化がもたらされていたよう。
しかも、展開部に入ったすぐの箇所では、冒頭の旋律がまたもや現れるのですが、それまでの2回以上に音量は絞られていて、抑制された音楽になっていた。その分、緊張度は随分と増すこととなっていた。更には、再現部での第2主題は、ほぼノンヴィブラートで演奏され、かつ、聴こえるか聴こえないかくらいにまで音量は絞られて、淡くて仄かな音楽として奏でられていた。その表情は、リピートされた提示部での演奏ぶりを、更に徹底したものとなっていたのでした。
尾高さんの表現しようと意図したものの本質、それは、展開部と再現部での演奏ぶりに秘められていたのではないだろうか。そのように思えたものでした。もっと言えば、提示部での音楽は、その前振りのようなものだったのではないだろうか、と。すなわち、シューベルトの音楽が持つ、繊細で、儚げで、ナーバスで、それでいて夢幻的だとも言えそうな性格を浮き彫りにするための、演奏上の設計だったのではないだろうかと思えてならなかったのでした。
正統的にして、決して穏当なものとはならずに、起伏に富んでいて、趣向を凝らした音楽を奏で上げていた、ここでの尾高さん。その≪未完成≫の演奏は、聴き応え十分なものであり、かつ、奥深いものでありました。
前半のシューベルトに大いに惹きつけられましたが、メインのブルックナーもまた素晴らしかった。その感銘度は、シューベルト以上でありました。
ブルックナーも、シューベルトと同様に、誠実さの滲み出ていた演奏でありました。全編を通じて、ケレン味のない演奏ぶりが貫かれていた。
そのうえで、凝縮度が高くて、かつ、豊穣な音楽が鳴り響いていた。カロリーが高くもあった。以前の尾高さんは、どちらかと言えば、スッキリとした演奏を聞かせてくれる指揮者だというイメージが強かったのですが、一昨年から尾高さん&大阪フィルの実演に頻繁に通うようになって以降は、カロリーの高さを感じさせてくれる演奏に何度か触れてきた。その観点から言えば、本日のブルックナーは、その最たるものだったように思えます。
総じて、ドッシリと構えた音楽づくりで、確固とした足取りでありつつも、輝かしくもありました。覇気に満ちてもいた。必要に応じて、躍動感を伴った演奏が繰り広げられていた。流麗でもあった。時にむせび泣くような表情を見せもする。その際の大フィルの弦楽器群は、艶やかにして豊かな音を鳴り響かせてくれていて、恍惚感が醸し出されてゆく。
それでいてやはり、第2楽章などは、音を打ち付けるように奏で上げていて、軽々しい音楽にはならない。弦楽器がコキコキと弾いてゆく(弓の使い方が、真っすぐでスピード感を伴っている)のも、心地よい。きっと、弾いている第フィルの団員のほうも、頗る気分よく弾いていたのではないでしょうか。
何よりも尊かったのは、表情がオーバーにならない、ということ。それは、尾高さんの、この曲への深い共感があったからこそ、ということなのでありましょう。流れが自然で、作品の内部から感興豊かな音楽が湧き出してくる、といった演奏だったとも言いたい。
唯一、ちょっと残念に思えたのは、第1楽章の主題提示部での第2主題に入った部分が、少し音楽が痩せて聞こえた点。総じて豊麗な演奏が繰り広げられていたのですが、この箇所だけが、多少なりとも隙間風が吹いていた感じ。音楽の流れがギクシャクとしてもいた。第2主題に入ってしばらくすると快調さを取り戻し、再現部で第2主題が現れた際にも隙間風を感じることはなかったため、何故あの箇所だけに、かような不満を感じたのかが不思議であります。
なお、シューベルトの弦楽器のプルト数は6-5-4-3-2.5でしたが、ブルックナーでは8-7-6-5-4。このような編成でブルックナーに臨んだことは、効を奏していたと言えましょう。厚みがあって、輝かしい響きを獲得していた演奏となっていました。
充実感いっぱいのブルックナーを聴くことができた。そのような幸福感を抱きながら、会場を後にしました。