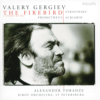井上道義さん&大阪フィルによる定期演奏会(ショスタコーヴィチの≪バビ・ヤール≫他)の第1日目を聴いて

昨日(2/9)は、井上道義さん&大阪フィルによる定期演奏会の第1日目を聴いてきました。プログラムは、下記の通り。
●ヨハン・シュトラウスⅡ ≪クラップフェンの森で≫
●ショスタコーヴィチ ≪ステージ・オーケストラのための組曲≫より
「行進曲(第1曲)」「抒情的ワルツ(第5曲)」「小さなポルカ(第4曲)」
「第2ワルツ(第7曲)」「第1ダンス(第2曲)」 の5曲
~ 休 憩 ~
●ショスタコーヴィチ 交響曲第13番≪バビ・ヤール≫
(バス独唱:ティホミーロフ、オルフェイ・ドレンガー男声合唱団)
今年の12月で引退することを表明している井上さん。残り限られた演奏の機会では、とにかく自分の演奏したい曲を採り上げていきたいと語っておられましたが、その言葉がストレートに響いてくるかのように、今回は、得意のショスタコーヴィチを主体としたプログラムが組まれています。
そのような中に、ヨハン・シュトラウスの短めのポルカを冒頭に置いているのが異彩を放っています。≪クラップフェンの森で≫、よほど思い入れの強い曲なのだろうと推測しつつも、大きな違和感が抱きながら会場へ向かったものでした。
会場に着いて、プログラム冊子を読んでいくと、合点がいきました。このポルカは、ロシアで作曲された作品とのこと。以下は、広瀬大介氏による解説を抜粋しての記載になります。
父ヨハンが逝去すると、それまでに父のもとでこなしていた仕事も息子のもとへ一極集中することになり、過労死寸前にまで追いつめられる。そのような中、1856年にロシアの鉄道会社と専属契約を結び、サンクトペテルブルク近郊の保養地、パヴロフスクでの演奏会を請け負うことになった。ヨハンは、この地で夏を過ごすことによって、楽団を養うに足る莫大な財産と、みずからの健康を手に入れたのであった。
ヨハンがパヴロフスクで作曲した作品は数多いが、純粋にこの地の名を冠した≪パヴロフスクの森で≫は、1869年に作曲、同地で初演された。そのポルカをウィーンで披露する際に、ウィーン郊外の丘の名を借りて≪クラップフェンの森で≫と改題されたのであった。
つまり、この日の演奏会でプログラミングされた作品は、ロシアで繋がることになるのです。しかも、前半の2曲は、舞踏的な要素の強い作品で統一されるという軸が生まれるという算段。
また、ショスタコーヴィチによる≪組曲≫について、広瀬氏による解説には、次のように書かれていました。
本作は、1950年後半頃、レフアフトミャンが、ショスタコーヴィチの了解のもと、映画音楽の演奏会用組曲の作成を手がけており、その折に成立したものと考えられている。かつては、1938年に作曲されたジャズオーケストラのための≪組曲第2番≫と混同され、楽譜は紛失したと考えられていた。1988年12月、ロンドン交響楽団、ロストロポーヴィチの指揮によって初演された際も≪ジャズ組曲第2番≫と呼ばれた。今回の演奏では、組曲の全8曲から、5曲が抜粋されて演奏される。
演奏会のチラシには、括弧つきで≪ジャズ組曲第2番≫と記載されていますが、この括弧は、そのような経緯によって付けられたようです。
なお、井上さんは、同一のプログラムを、同一の独唱者と合唱団と共に、先週の土日にN響の定期演奏会でも採り上げていたようです。

前置きが長くなりました。ここからは、この日の演奏について触れてゆくことに致しましょう。
冒頭の≪クラップフェンの森で≫は、先にも書きましたように、ロシアで作曲されたポルカだということで、この日のプログラムに一定の一貫性が保持されています。しかしながら、客席に座って聴いていますと、もっと深い意図があるように思えてきた。と言いますのも。
この日のメインは、≪バビ・ヤール≫という、ウクライナのキーウにある渓谷のバビ・ヤールで、ナチス・ドイツがユダヤ人を大量虐殺したという、実際に起きたとは思いたくない史実を題材に採った、凄惨な音楽。そうであるだけに、ヨハン・シュトラウスの夢見心地な気分にさせられる音楽を冒頭に持ってきて、聴き手の気持ちを軽くしようとしたのではないだろうか。更に言えば、今夜は、架空の世界に(すなわち、史実から懸け離れた空想の世界に)誘われたかのような気持ちを聴き手が抱くべく、プログラミングされたのではないだろうか。今回の選曲を、そんなふうに捉えながら聴いていたものでした。
その演奏はと言えば、井上さんらしいサービス精神旺盛なものでした。愛嬌たっぷりであった。しかしながら、シュトラウスファミリーの音楽を日本人が演奏する難しさを痛感させられもした。リズム感や、音楽に対するノリや、といったものが板に付いていなかったように思えてならず、わざとらしさが匂ってきたのであります。
2曲目のショスタコーヴィチの≪組曲≫も、メインの≪バビ・ヤール≫を中和させるための選曲だったのでしょう。ショスタコーヴィチが映画のために作曲した小さな音楽を集めて編まれた組曲なだけに、娯楽性の高い音楽でありました。こちらでは、エンターテイナーとしての井上さんの魅力が、ストレートに生きていた。
それは、カバレフスキーの≪道化師≫や、ハチャトゥリアンの≪仮面舞踏会≫を思わせるようであった。実際に、曲調も頗る似ている。そのような中で、最後に演奏された「第1ダンス」は、ショスタコーヴィチの≪祝典序曲≫を彷彿とさせもした。
また、アコーディン、ギター、更には4本のサクソフォンと、通常のオーケストラではなかなか組み込まれない楽器が大活躍して、ムーディでもあった。
ナンバーによって、快活であったり、哀愁に満ちていたりと、コントラストが鮮やかな組曲。そのような作品を、表情豊かに、かつ、お茶目に演奏してゆく井上さん。とても敏捷性が高くもあった。
そんなこんなによって、大いに楽しみながら聴くことができました。
それでは、メインの≪バビ・ヤール≫について。
いやはや、素晴らしい演奏でした。凄絶な演奏でありました。聴いていて、打ちひしがれながらも、最後は浄化されるかのようでした。
それにしましても、≪バビ・ヤール≫、凄い曲ですね。
とりわけ、第2楽章の「ユーモア」は、戦慄ものでした。終始、おどけていながらも、その裏には苦悩が隠されていて、賑やかに演奏すればするほどに、慟哭する音楽を聴いているかのような気分になる。そのような音楽は、井上さんの大の得意とするところだと言えるかもしれません。屈託がなく、思いっきり陽気に、演奏を展開してゆくのです。更に言えば、オケを存分にドライブしながら、大音響で賑々しく音楽を奏で上げてゆく。そのような演奏ぶりによって、切実な音楽が出現する。外観が陽気であるだけに、よけいに、聴いていて、いたたまれなくなってきたものでした。
かような第2楽章での演奏に限らず、全編を通じて、敏捷性の高い演奏を繰り広げてくれていました。それは、前半での≪組曲≫での演奏ぶりが引き継がれていたようなもの。そこに、≪バビ・ヤール≫では、切実さが加えられていた。エンターテイナーとしての演者というよりも、もっと、共感性の高い演奏ぶりだったとでも言えば良いのでしょうか。
今、これを書きながら考えてゆくうちに、井上さんは、道化的な要素があるのかもしれないと思えてきました。それ故に、真実味を打ち出した演奏を展開すると、悲哀を帯びてくるようになる。そう、第1楽章をはじめとして、実に悲哀を帯びた音楽が奏で上げられていた。頗る逞しい演奏ぶりで、鮮烈でありつつも、開放的になることなく、求心力の強い演奏でもあった。
そのような井上さんの音楽づくりに対して、バス独唱のティホミーロフがまた、素晴らしかった。その歌いぶりは、井上さん以上に真実味に満ちていたように思えたものでした。そして、自在感に溢れていた。
声は太くて、朗々としている。しかも、馬力に溢れている。それでいて、ソフトに歌うべき箇所では、実に柔らかな声を響かせてくれる。
そのうえで、共感性の高い歌唱を繰り広げてくれていた。劇性が高く、かつ、深々としてもいた。
初めて名前を聞くバス歌手でありましたが、この曲をかなり歌い込んでいるのでしょう。
(プログラム冊子には、ムーティ&シカゴ響とも、この曲を演奏していると書かれていました。また、帰宅してネットで調べてみますと、そのときの演奏がライヴ録音され、CD化されているようです。)
ワールドクラスの歌唱だったと思えます。
また、スウェーデンから招いた男声合唱団も、力強さと繊細さを兼ね備えていて、素晴らしかった。
≪バビ・ヤール≫の真髄のようなものを、存分に味わうことのできた演奏でありました。
メインの≪バビ・ヤール≫に圧倒された演奏会。しかも、プログラムの妙が感じられもした。なるほど、≪バビ・ヤール≫から受けた感銘が破格であっただけに、前半の2曲が霞んでしまったような感が強くもありますが、思い返してみると、前半の2曲が、いい味を出してくれてもいる。
いやはや、聴きに来た価値が十二分にあった、大満足な演奏会でありました。
余談ではありますが、前半が終わっての休憩中にスマホを開くと、小澤征爾さんが逝去されたというニュースが画面に現れました。なんという、ショックなこと。
小澤さんの訃報に触れることになったという意味でも、忘れがたい演奏会になりそうです。