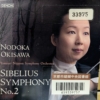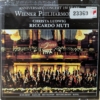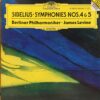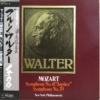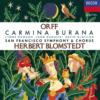堀米ゆず子さん&ゴムツィアコフ&田村響さんによるピアノ三重奏の演奏会(モーツァルト、ショスタコーヴィチ、チャイコフスキー)を聴いて

今日は、兵庫県立芸術文化センターで、堀米ゆず子さん&ゴムツィアコフ&田村響さんによるピアノ三重奏の演奏会を聴いてきました。演目は、下記の3曲。
●モーツァルト ピアノ三重奏曲第6番
●ショスタコーヴィチ ピアノ三重奏曲第2番
●チャイコフスキー ≪偉大な芸術家の思い出に≫
チェロのゴムツィアコフは初めて名前を聞く奏者ですが、堀米ゆず子さんと田村響さんとがトリオを組むという、豪華な顔合わせによる演奏会。「ブリリアントな仲間たち」という謳い文句もシックリきます。
しかも、メインのチャイコフスキーの≪偉大な芸術家の思い出に≫のみならず、モーツァルトとショスタコーヴィチの作品も採り上げるという、ピアノ三重奏曲の中でも屈指の名品を揃えたプログラムになっているところが、なんとも魅力的であります。
田村さんによる≪偉大な芸術家の思い出に≫は、2022年2月にびわ湖ホールで、竹澤恭子さんと宮田大さんと組んでの演奏を聴いています。それはもう、白熱の演奏でありました。しかも、単に熱が籠っているだけではなく、全編を通じて、実に表情の濃い演奏となっていた。そう、誠に多彩な演奏であった。スリリングであり、かつ、聴く者の魂を揺さぶるような「真実味」のある演奏となっていた。そのような演奏ぶりの中で、田村さんは、ヴァイオリンとチェロを包み込むようにして弾いていった。それは、知情のバランスに優れたピアノ演奏だったとも言いたい。
そのうえで、堀米さんと田村さんが加わっての演奏ということで、真摯な音楽が奏で上げられるのであろうと想像したものでした。
はたして、本日はどのようなピアノ三重奏を聴くことができるのだろうか。ドキドキワクワクしながら会場に向かったのでありました。
それでは、本日の演奏会をどのように聴いたのかについて書いてゆくことに致します。

まずは前半の2曲から。
想像していた通りの、真摯な態度が貫かれていた演奏となっていました。そのうえで、誇張がなくて、端正な音楽が鳴り響いていた。
冒頭のモーツァルトでは、まずもって、田村さんのピアノが頗る清冽なものになっていて魅了されました。そのことが、ここでの演奏を特徴づけていたと言いたい。それ故に、とても無垢で可憐なモーツァルト演奏となっていました。柔和でいて、キリッとした表情を湛えてもいた。
そのような田村さんのピアノに、堀米さんの艷やかなヴァイオリンと、ゴムツィアコフの朗々と響くチェロとが絡んで、優美で気品漂う演奏が展開されたのでありました。
その一方で、ショスタコーヴィチでは、この作曲家の作品に相応しい凄絶さが加わっていました。切れ味の鋭さが感じられもした。とは言うものの、ヒステリックになるようなことはない。そう、端正な佇まいを保った上で、鋭さを備えた演奏が繰り広げられていたのであります。更には、ショスタコーヴィチに特有のシニカルな雰囲気を帯びた箇所では、大袈裟になることはなかったものの、的確に表現されていた。
しかも、十分にドラマティックだった。必要に応じて、強靭な音楽が鳴り響いてもいた。
ここでは、モーツァルトでの演奏以上に、チェロが表情豊かで、奥行き感のある音楽を奏でていて、ゴムツィアコフの技巧の確かさや、音楽性の豊かさが実感されたものでした。
こうなると、メインのチャイコフスキーがいよいよ楽しみだな。そんな思いを抱きながら、休憩時間を過ごしたものでした。
それでは、ここからはメインのチャイコフスキーについて。それは、期待していた以上に素晴らしい演奏となっていました。
前半の2曲と同様に、誠実さの滲み出ている演奏となっていました。そのうえで、この作品ならではの、多様な性格がクッキリと刻まれていた。そして、白熱の演奏が展開された。
まずもって、冒頭のチェロによる旋律に酔いしれました。ゴムツィアコフのよる演奏は、実に朗々としていて、息遣いが豊かで、かつ、しなやかだった。とてもノーブルで、歌謡性が高くもあった。そのことによって、この作品の音楽世界に、なんの差し障りもなく入り込むことができたものでした。
モーツァルトでは可憐な演奏が、ショスタコーヴィチでは凄絶な演奏が繰り広げられていたのですが、チャイコフスキーではロマンティックにして抒情性に満ちた演奏ぶりが示されていた。しかも、力強さにも不足がなく、広壮な音楽が奏で上げられていた。情念の深さのようなものも添えられていた。すなわち、本日プログラミングされていた3つの作品の、それぞれに異なる性格を、明確な形で描き分けられていたのだった。そんなふうに言いたくなります。しかも、とても質の高い状態で。
なるほど、チャイコフスキーでは情念的な演奏が繰り広げられていました。しかしながら、決してドロドロとしたものになっていませんでした。そう、ここでも端正な音楽づくりが失われていなかったのであります。
しかも、例えば第1楽章の第2主題では、田村さんは前半では見せなかったような強靭なタッチを繰り出していた。そのことによって、実に豪壮な音楽が鳴り響くこととなっていました。それでいて、響きが混濁するようなことはなかった。コケ威しな音楽になるようなこともなかった。ピュアな美しさを保っていたのであります。
例えば、第1楽章の展開部の途中に出てくる儚さを湛えた箇所では、実に肌触りの柔らかな音楽が鳴り響いていた。
例えば、第1楽章の再現部に入った箇所では、諦観の表情がクッキリと刻まれていた。
かように、この作品に備わっている多様な性格が鮮やかに描き出されていたのであります。
そのような細やかな表情付けは、長大にして多面的な性格を持つ第2楽章において、更に鮮明な形で表されていったのであります。
時に力強く、時に軽やかに、時に朧げに、時に抒情性豊かにと、変幻自在に表情を変えてゆく。しかも、それらが全くワザとらしくない。頗る自然な形で提示されていたのであります。それも、豊かな息遣いを伴って。
その先に現れる終曲では、壮麗にして生命力豊かな音楽が鳴り響くこととなっていた。頗る輝かしくもあった。ダイナミックでもあった。そして、第1楽章が戻ってくると、重厚にして壮絶な音楽が奏で上げられた。曲が閉じられる場面では、沈鬱な表情を見せてくれもする。繰り返し書くことになりますが、そのような演奏ぶりにワザとらしさが微塵も感じられない。共感に満ちた音楽が鳴り響いていたのであります。そのことによって、聴き手はこの作品の音楽世界を等身大の姿で触れることができることとなる。
ここからは、それぞれ奏者について触れてゆくことに致しましょう。
このトリオをリードしていたのは田村さんだったのではないでしょうか。繊細な音楽づくりから、豪壮な音楽づくりまで、実に幅の広い表現を示してくれていたものでした。しかも、清冽な性格をベースにしたものになっていた。とてもピュアであった。音の粒がクッキリとしていて、結晶度が高くて、それでいて鋭くなり過ぎることがなく、まろやかな響きをしていた。
本日の演奏では、その大半を、主として田村さんのピアノに耳を傾けながら、音楽の流れや、演奏の機微や、といったものを追いかけていったものでした。
堀米さんは、ヴァイオリンという楽器に特徴的な艷やかさを存分に感じさせてくれる演奏を繰り広げてくれていました。しかも、頗るしなやかでもあった。その一方で、音楽が情念的な性格を帯びる際には、堀米さんによる貢献が高かったように感じられたものでした。
そのうえで、音楽のフォルムが崩れることは皆無でした。それは、堀米さんの音楽性の高さ故なのだと言いたい。
チェロのゴムツィアコフもまた、艷やかな美音の持ち主でありました。しかも、とても伸びやかに音楽を奏で上げてゆく。押し付けがましさは全くなく、ノーブルな音楽を鳴り響かせていた。柔軟性が高かったとも言いたい。プログラム冊子のプロフィールを読みますと、ピリスやデュメイともピアノ三重奏を組むこともあるようで、室内楽奏者としてのツボのようなものを心得ているチェロ奏者だな、とも感じられたものでした。その一方で、ソリストとしてのゴムツィアコフにも是非とも接してみたいものだと思えたものでした。
アンコールは、メンデルスゾーンピアノ三重奏曲第1番から、緩徐楽章となる第2楽章。
こちらでは、抒情的な美しさを前面に押し出したものになっていました。清潔感に溢れていた。そして、可憐でもあった。
この3人によるアンコールとしては、うってつけだったのではないでしょうか。