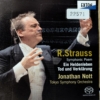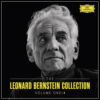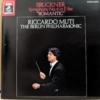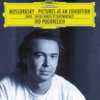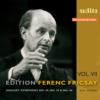沖澤のどかさん&読響によるシベリウスの交響曲第2番を聴いて
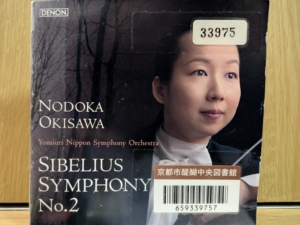
沖澤のどかさん&読響によるシベリウスの交響曲第2番(2021年ライヴ)を聴いてみました。
図書館で借りたCDでの鑑賞になります。
テンポは、やや遅め。そのこととも関連して、呼吸の深い演奏になっています。とは言いましても、遅めのテンポを押し通している訳ではなく、必要に応じて音楽を煽っており、そのことによってテンポが速められることもしばしば。
しかも、ダイナミクスの変化も著しい。その象徴的なシーンとして、第2楽章冒頭での、弦楽器群によるピチカートが挙げられましょう。この箇所を沖澤さんは、クレッシェンドとデクレッシェンドとを交錯させながら、大きな起伏を付けています。その強弱の幅は、とても大きい。そのことによって、音楽にメリハリが付くこととなっている。この箇所を、こんなにも思い切った表情付けしてゆくことは、あまり前例を見ません。沖澤さんの嗅覚の鋭さのようなものを感じ取ることができたものでした。
この冒頭部分に限らず、第2楽章での演奏は、とても振れ幅の大きなものとなっています。沈鬱とした感覚と、昂揚感との間を、何度も行き来する演奏となっている。とても感傷的でありつつも、必要に応じては頗るドラマティックな音楽を響かせてゆく。しかもそれらが、決して大袈裟なものにはなっていない。それは、作品への共感の深さ故なのでありましょう。
或いは、第3楽章では頗る機敏な演奏が繰り広げられながら、第3楽章から最終楽章へと移行する箇所では、大きな昂揚感が打ち出されています。そのうえで、最終楽章では、壮麗な音楽づくりを施しつつ、曲想に応じては悲哀に満ちた表情を見せたり、輝かしさを前面に押し出したりしている。そして、クライマックスでは、堂々としていて、かつ、感興の豊かな音楽が鳴り響いている。
更には、これは全楽章を通じて言えることなのですが、音楽が随所でうねっている。
そのようなことも含めて、呼吸の深い演奏になっていると言いたい。
そのような音楽づくりが認められる一方で、沖澤さんならではの、几帳面さや、誠実さや実直さが備わった演奏となっています。なるほど、ここでの演奏では、かなりアグレッシブな表現が採られている。しかしながら、そういった表現が粗さに繋がるようなことはない。或いは、作品の枠を超えるようなこともない。そのうえで、演奏をシッカリと磨き上げてゆこう、といった責任感の強さのようなものを感じ取ることができる。
驚くべきことに、この音盤は、沖澤さんが読響の指揮台に初めて登った演奏会を記録したものだそう。初めて指揮するオケを見事に掌握している手腕の確かさには、目を瞠るものがあります。
沖澤さんの指揮者としての力量がシッカリと理解できる音盤。そんなふうに言えるのではないでしょうか。そのうえで、この作品の魅力を存分に味わうことのできる、素敵な演奏となっています。