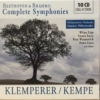HIMARIさんをソリストに迎えての、デ・フリーント&京都市交響楽団による定期演奏会の第2日目を聴いて

今日は、デ・フリーント&京都市交響楽団による定期演奏会の第2日目を聴いてきました。演目は、下記の3曲。
●ドヴォルザーク ≪ロマンス≫(Vn独奏:HIMARIさん)
●ヴィエニャフスキ ≪ファウスト幻想曲≫(Vn独奏:HIMARIさん)
●モーツァルト ≪レクイエム≫
(ソプラノ:石橋栄実さん、メゾ・ソプラノ:中島郁子さん、テノール:山本康寛さん、バス:平野和さん)
本日の演奏会、チケット発売の翌日には完売になっていました。並外れた注目度の高さだと言えましょうが、それと言いますのも、今年14歳になったヴァイオリニストのHIMARIさん(本名は吉村妃鞠)がソリストとして登場するがためだったと思われます。
3月にベルリン・フィルの定期演奏会に呼ばれて、ヴィエニャフスキのヴァイオリン協奏曲第1番を弾いたHIMARIさん。話題性十分であります。そのHIMARIさんが、前半でドヴォルザークとヴィエニャフスキの作品を披露してくれる、本日の演奏会。彼女のヴァイオリン演奏を聴くのは初めてでありますが、その演奏ぶりはどうなのだろうか。そのことが、第一に興味を惹かれる点でありました。
指揮は、2024-25年シーズンより京響の首席客演指揮者を務めているデ・フリーント。同ポストに就任して以来、京響の定期演奏会を指揮するのは3回目になります。古楽系のオーケストラを主に指揮してきたデ・フリーントが、モーツァルトの≪レクイエム≫をどのように演奏するのか。そちらも興味深いところでありました。なおかつ、前半と後半でガラリと肌合いの異なる作品を並べているだけに、そのようなプログラムでデ・フリーントがどのような手綱さばきを見せてくれるのかにも、注目していた。
そんな、好奇心を掻き立てられる演奏会。ドキドキワクワクしながら、会場に向かったものでした。
それでは、本日の演奏会をどのように聴いたのかについて、書いてゆくことに致しましょう。

まずは前半の2曲から。
HIMARIさん、楽器をシッカリと鳴らしながら、豊かな響きで音楽を奏で上げていました。それは、1曲目のドヴォルザークで、最初の音を鳴らした時点でハッキリと確認できた。
しかも、高い技巧を備えていて、安定感抜群の演奏を繰り広げていた。と言いつつも、テクニックをこれ見よがしに誇示するようなことはない。すなわち、曲芸的なヴァイオリン演奏になるようなことは皆無でありました。その辺りも、なかなか立派なことだと言いたくなりますし、HIMARIさんの音楽への真摯な態度、といったようなものを窺うこともできた。
そのような美点を認めることができつつも、その一方で、作品に依るところも大きかったのでしょうが、全体的に平板な音楽づくりに思え、聴いていて惹きつけられるようなことはなかった。総じて、起伏に乏しい音楽になっていたのであります。なるほど、息遣いが自然で、素直な音楽づくりではありました。しかしながら、呼吸の深い音楽だったとは言えそうになかった。更に言えば、音楽が型に嵌まり過ぎていて、伸びやかさに乏しかったようにも思えた。
ドヴォルザークの≪ロマンス≫を聴いている間は、このような印象を持つのも、作品の構成に依るのだろうと考えていたのですが、起伏に富んでいて、彩りの豊かなヴィエニャフスキの≪ファウスト幻想曲≫に移っても、印象は変わらなかった。曲ももう終わろうとしているところで現れる、フラジオレットで奏でてゆく箇所では、音が痩せずに艷やかに響き渡っていて、大いに魅了させられたのですが。
そんなこんなもあって、事前に抱いていた期待を満足させてくれたとは言い切れないヴァイオリン演奏だった、というのが正直なところでありました。
なお、デ・フリーントによるバックアップは、ツボを押さえたものだったと言えましょう。過度に音楽を誇張するようなところは皆無でありつつ、生気に溢れた音楽を奏で上げてくれていて、見事なサポートぶりでありました。
ソリストアンコールは、イザーイの無伴奏ヴァイオリンソナタ第6番から。
こちらでは、前の2曲以上に音楽がシッカリと躍動していたように思えました。技巧の高さも、より一層際立っていた。しかしながら、呼吸の深い音楽だったとは思えなかった。その点で、前の2曲での印象そのままの演奏でありました。
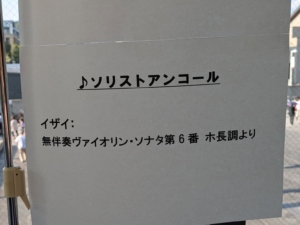
それでは、ここからはメインのモーツァルトの≪レクイエム≫について。いやはや、なんとも素晴らしい演奏でありました。
京響を指揮するデ・フリーントを聴くのは、これが3回目。その中で、最も強い感銘を受けたものとなりました。これまでの演奏会では、正直なところ、前任のアクセルロッドが首席客演指揮者を辞任した寂しさを覚えることが多少なりともあったのですが、この≪レクイエム≫を聴いている間は、そのような思いを抱くこと全くなかった。
特徴的だったのは、古楽の流儀がかなり採り入れられている音楽づくりになっていた、ということ。まずもって、弦楽器は対向配置が採られていた。また、ティンパニは硬いバチが使われていて、トランペットとともに、頗る衝撃的に打ち鳴らされることが多かった。また、速めのテンポを基調としていて、清新にして、粘るようなことの微塵のないスタイルが貫かれていた。
そのような音楽づくりの元、立体的で、かつ、推進力に満ちた音楽が奏で上げられていったのであります。例えば、キリエでのフーガの動きは、合唱団と共に吹いてゆくトロンボーン群が明瞭に聞こえてきていた。そのことによって、旋律線が見事なまでに補強されていて、音楽に逞しさが備わることとなっていた。鮮明な音楽になってもいた。なおかつ、目くるめくような音楽が鳴り響くことになっていた。
と言いつつも、誇張は感じられなかった。総じて、ケレン味がなく、かつ、頗る剛健な音楽が鳴り響くこととなっていた。そのうえで、聴いている間じゅう、「なんと素晴らしい音楽なのだろう」といった感慨を抱くことができた。
キビキビとしていて、潔さのようなものが備わっていた演奏。ハッタリが一切無い演奏ぶりであり、とても真摯な音楽になっていた。
しかも、優しさに満ちてもいた。なるほど、ディエス・イレでのティンパニなどは、強烈に打ち込んでいて、ティンパニによる一撃を合図にオケが束になって突撃を始める、といった様相を呈することもあったのですが、決して粗暴な音楽にはなっていなかった。いや、それによって、生気に溢れた、そして、輝かしい音楽が繰り広げられることとなっていた。更には、ラクリモーサでは、音楽が決して停滞することなくサラサラと流れてゆく(それでいて、無為に流れる訳ではない)のですが、慈しみに満ちていた。
そのうえで、キリエをはじめとして、各ナンバーの最後の箇所で、他の多くの演奏では合唱団が力強く歌い上げることが多いところを、音をしぼませながら、柔和な表情を与えながら、それぞれのナンバーを閉じてゆく。そのような処理は、最後の最後でも変わらない。
(ここだけは、音をしぼませずに、輝かしさを保ちながら全曲を閉じるのかな、などと想像していたのですが、そうではなかった。)
そのようなこともあって、柔らかさと共に、敬虔な雰囲気を持つことになってもいた。
そんなこんなを含めて、この作品の音楽世界にドップリと身を浸すことのできる演奏が繰り広げられていたのであります。
そのようなデ・フリーントの卓越した演奏ぶりに加えて、独唱陣もまた、見事でありました。
モーツァルトにしては珍しく、と言いましょうか、比較的、声量の豊かさを備えた、強い声を持った歌いぶりだった、と言えそう。特に、メゾ・ソプラノの中島さんと、バスの平野さんに、その傾向が強かった。中島さんなどは、アズチェーナやサントゥッツァを想起させられるような芯の強さのようなものが感じられた。
(2018年にバッティストーニ&九州交響楽団による≪カヴァレリア・ルスティカーナ≫で、中島さんのサントゥッツァを聴いていますが、凛としていて、情感の豊かな歌いぶりに、大いに魅せられたものでした。)
それでいて、4人ともに、モーツァルトの≪レクイエム≫の音楽世界を逸脱するようなことはなかった。すなわち、力強くありつつも、清澄な歌を繰り広げてくれていたのであります。そして、とても真摯でもあった。
指揮者にも、独唱陣にも、大いに感心させられた≪レクイエム≫でありました。