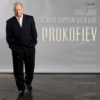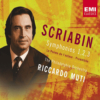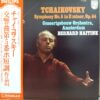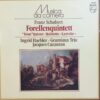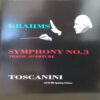インバル&大阪フィルによる演奏会の初日(マーラー交響曲第10番・クック版)を聴いて
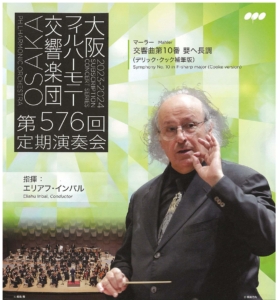
今日は、インバル&大阪フィルによる定期演奏会(初日)を聴いてきました。インバルと大阪フィルは、初めて共演したのが2016年のこと。今回で4回目になるようです。
演目は、マーラーの交響曲第10番(クック版)の1曲プロ。
インバル得意のマーラー。先週は都響と、本日と同じく第10番のクック版を演奏しています。そちらの演奏会を聴きに行かれた知り合いのお話ですと、かなり素晴らしかったようです。
インバルは、細部をキッチリと磨き上げながら、ソツなく纏め上げる指揮者、という印象が強い。仕上がりは頗る美しい。そして、端正で、流麗で、スッキリとした佇まいを示してくれる。
そのような特徴を持ちながら、2010年以降辺りから、逞しさを増し、かつ、音楽にコクを与えてくれるようになったと思えます。
なお、1936年の2月生まれということで、先月に88歳(日本流に言えば米寿になりますね)になられています。小澤征爾さんの5ヶ月後に生まれたということにもなります。
ところで、ここでお伝えしておきたいこと、それは、個人的にはどうも、クック版は、その音楽世界に没入できないということ。第1楽章のアダージョだけで、私は十分だと思えてしまいます。もっと言えば、第2楽章以下は、なんと言いましょうか、取ってつけた感が拭えない。
と言いつつも、ザンデルリンク&ベルリン響盤(1979年録音)を聴いたときは、全5楽章を通じて、充実感タップリな演奏ぶりに感銘を受けたものでした。実に真摯で、峻厳な演奏が繰り広げられていた。散漫にならずに緊張感が強く、彫りが深くて、シリアスでもあった。このときばかりは、5つの楽章全てにおいて共感ができ、マーラーの10番はアダージョだけで十分、という思いから解き放たれたものでした。
そのようなクック版も、実演で接するのは本日が初めて。はたしてインバルが、クック版でどのような演奏を繰り広げてくれることだろうか(私自身が抱いている「クック版の呪縛」のようなものから解放してくれるものだろうか)と、期待に胸を膨らませながら会場に向かったものでした。

それでは、本日の演奏について触れることに致しましょう。
まずもって、インバルは実に矍鑠とされていました。ステージを闊歩する足取りや、終演後にパートごとに団員を起立させる仕草や、などなど、実にシッカリとしていた。演奏ぶりも、インバルが急速に注目を集めるようになった1980年代のもの(その時期に、マーラーやブルックナーなどで聞かせてくれた演奏)を思い出させてくれるものでありました。そう、その当時のインバルの演奏スタイルそのままで、流麗でスッキリとしたものでありました。
何よりも、インバルらしさが痛切に感じられたのは、音楽が粘ったり、停滞したり、というようなことは殆どなく、淀みなく流れていた点。キビキビとしてもいた。ある種、健康的だったとも思えた。音が鳴り止んだ時点で時計に目を遣ると、演奏時間は、70分ほどだったようでした。キビキビと進められていたことを、このタイムが裏付けていると言えましょう。
それでいて、音楽が上滑りするようなことはない。基本的には、陽性で、清々しい演奏ぶりに思えたのですが、感興に不足するようなこともなかった。速めのテンポを基調としていながらも、適度にアゴーギクを効かせながら、鬱屈としたものにならない範囲で陰影が付けられてゆく。目鼻立ちがクッキリとしてもいた。そして、劇性や、逞しさや、鮮やかさも、必要十分に備わっていた。
そのような演奏ぶりを通じて、最晩年のマーラーの作品に特徴的と思われる厭世感のようなものが少なからず漂ってきた。しかしながらそれは、「絶望的」といったものとは異なる音楽として聞こえてきたのが、インバルらしいところだと言えそう。例えば、第2,4楽章のスケルツォでは、かなり明朗な音楽世界が広がっていて、インバルの体質に適したものだったように思えた。
やるべきことを、インバルならではのやり方で丁寧に実行していた演奏。そんなふうに言えましょう。しかしながら、第1楽章のアダージョ以外はどうも、音楽の焦点のようなものが定まらない、といった印象は拭え切れませんでした。そして、散漫な音楽に聞こえてしまった。そう、私が捕らわれている「クック版の呪縛」から解放されることはなかった。
(ザンデルリンクのように、もっとシリアスであり、峻厳な雰囲気が立ち込めるような演奏ぶりだと、印象は変わったのかもしれませんが。)
心が満たされない思いで、会場を後にしたものでした。